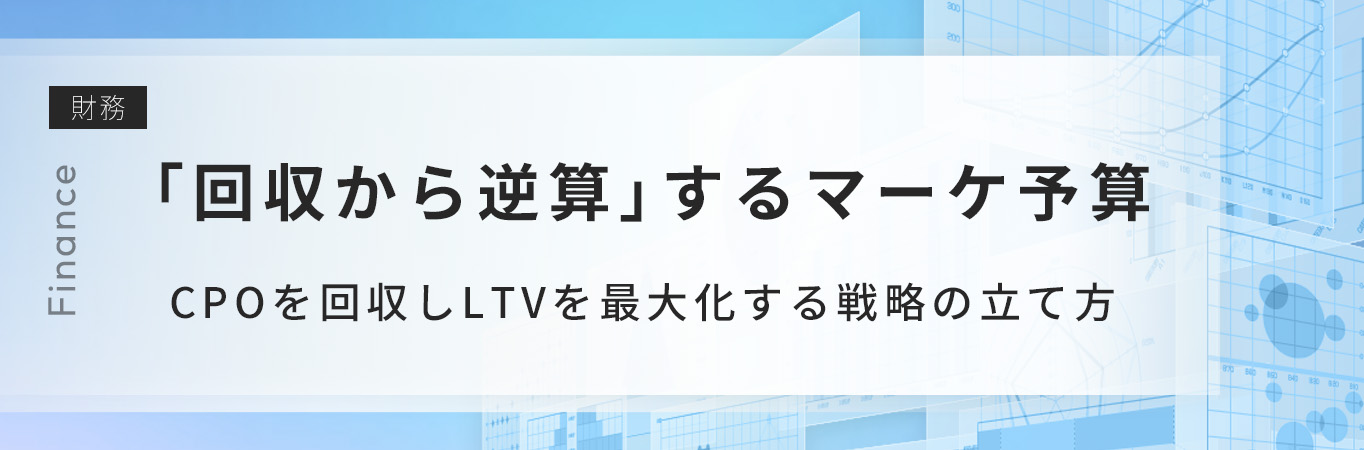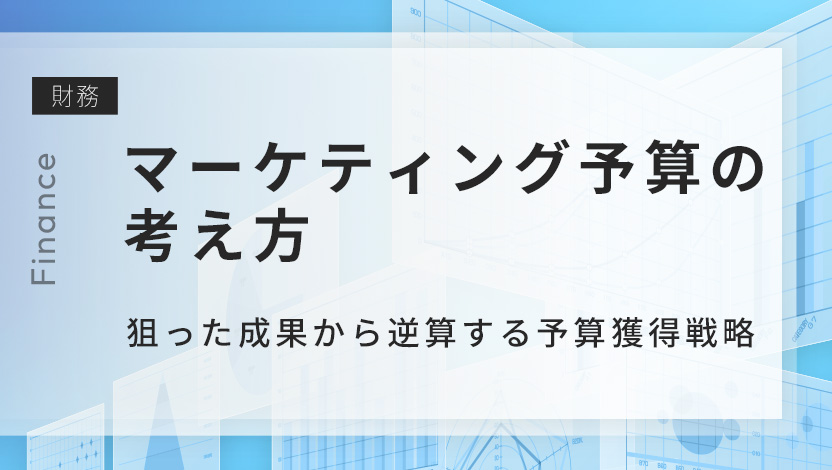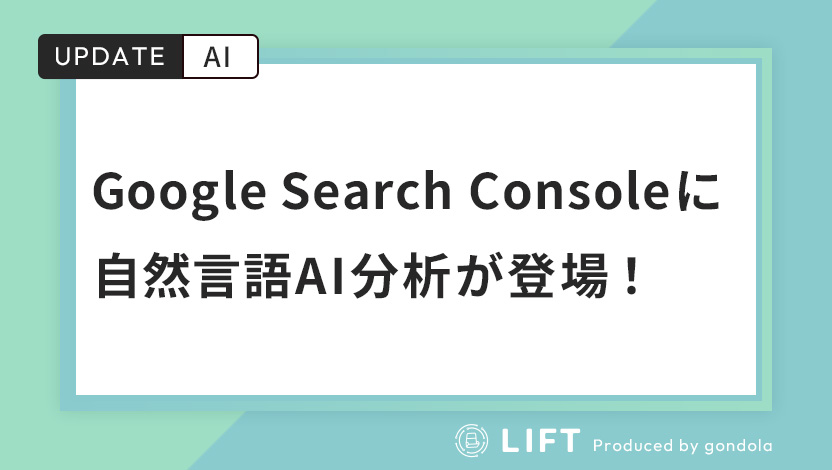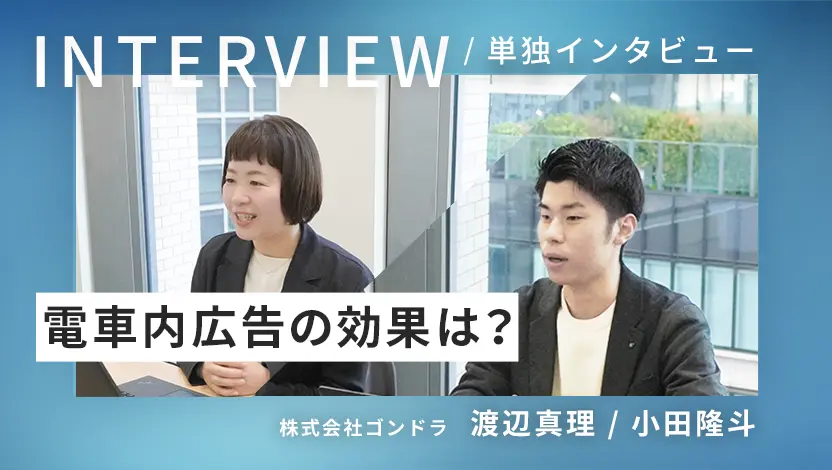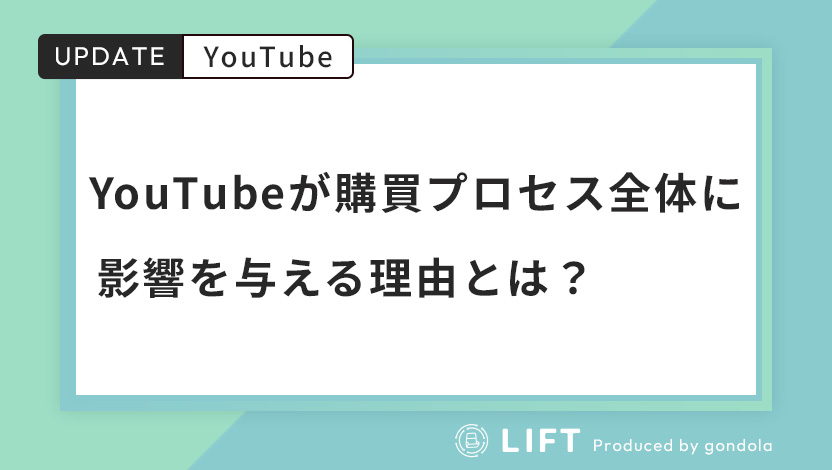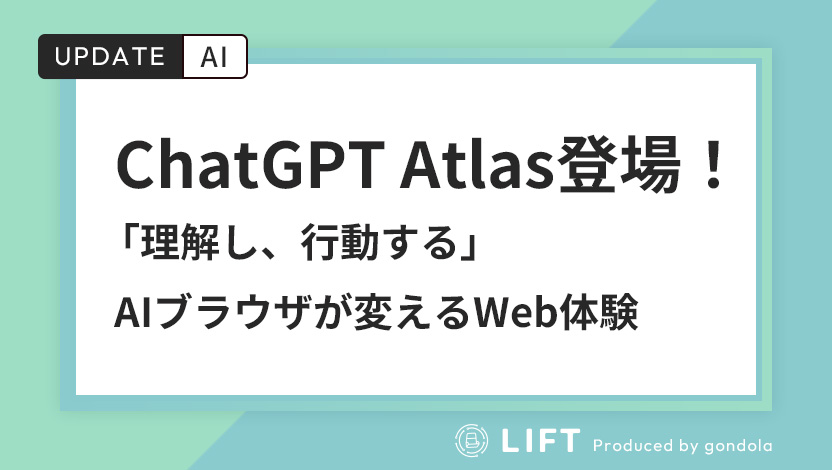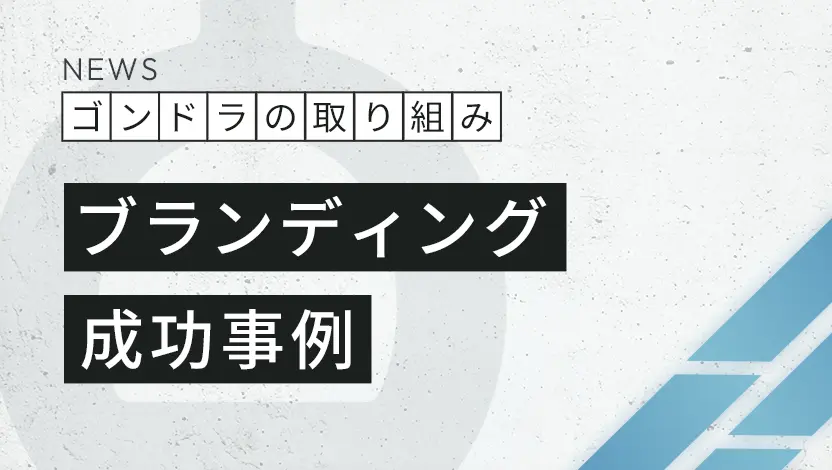マーケティング施策の立案にあたっては、投資した予算以上の効果が得られることを前提として、健全なキャッシュフローを維持するためのコストの回収サイクルを考え、施策の効果を最大化できるように計画を立てます。
そこで重要な指標が、CPOとLTVです。
本記事では、この2つの指標を基にして、マーケティング施策の効果を最大化するための考え方と、具体例を紹介します。
マーケティング予算の考え方の基本
マーケティング施策は、投資以上の効果が得られることが予算獲得の前提です。その上で、効果がより大きくなるよう、費用対効果の最大化を考える必要があります。
マーケティング施策の費用対効果を考えるには、ROIを算出します。ROIは、かけたコストに対して得られた成果を利益率として算出したものです。なお、広告運用については一般的にROASという指標が使われます。
また、健全なキャッシュフローを保つためには、どのくらいの期間で投資以上の効果がでるのか、すなわち予算投資の回収サイクルを考えることが重要です。最終的に投資以上の効果が得られるとしても、回収に時間がかかりすぎると資金繰りが苦しくなってしまいます。
その上で、マーケティング施策を事業の成長につなげていくためには、予算投資を回収することは前提として、さらに多くの利益が得られるよう考える必要があります。
予算投資・回収サイクルを考えるために必要な指標
マーケティング施策の予算投資について、その回収サイクルを考えるにあたり、理解しておきたい指標が「CPO」と「LTV」です。
CPO
CPOは「Cost Per Order」の略で、注文1件を獲得するためにかかるコストのことです。特に、新規顧客を獲得するためのコストを算出する際に活用される指標です。マーケティング予算の投資を回収することは、すなわちCPOを回収することを意味します。
CPOは、以下の式により算出できます。
CPO=施策にかかったコスト/施策で獲得した新規顧客数
これから行う施策についてCPOを算出するときは、過去に実施した施策など関連するデータを参考にして、「対象となる施策にかかると想定されるコスト/その施策で想定される新規顧客獲得数」でCPOを求めます。
CPOは、広告の費用対効果を測る指標としてよく使われます。広告以外にも、注文獲得に直接つながる施策については、CPOを費用対効果を測る指標として活用できる指標です。
CPOとCPA
CPOによく似た指標に「CPA」があります。CPAは「Cost Per Action」の略で、CV(コンバージョン)1件を獲得するためにかかるコストのことです。
CVには、注文獲得だけでなく会員登録や資料DLなどさまざまな顧客の行動が設定されるので、CPAは幅広いマーケティング施策のコスト算出に役立ちます。なお、CVを注文獲得とした場合は、CPO=CPAとなります。
CPOとCAC
CPOによく似た指標として「CAC」という指標もあります。CACは「Customer Acquisition Cost」の略で、顧客1人を獲得するためにかかったすべてのコストのことです。
CPOが広告などマーケティングの施策単位で使われる指標であるのに対し、CACはマーケティング事業全体あるいは会社全体などより大きな範囲で使われる指標です。CACには広告費などの顧客獲得に直接的に貢献するコストだけでなく、人件費などの間接的なコストも含みます。
LTV
LTVは「Life Time Value」の略で、1人の顧客が企業と取引する全期間においてもたらされる利益のことです。
マーケティング予算の投資を回収するためには、CPO<LTVとなる必要があります。新規顧客獲得にかかったコストよりも、その顧客からもたらされた利益のほうが大きくなった状態が、CPOを回収できた状態です。
ただし、CPO回収に時間がかかりすぎると、キャッシュフローが悪化してしまいます。そうならないよう、CPOをどれくらいの期間で回収できれば、健全なキャッシュフローを保てるのかを考える必要があります。
さらに、マーケティング施策を事業の成長につなげるためには、CPOを適切な期間で回収した上で、LTVの最大化を目指すことが大切です。
LTV算出の基本
LTVの基本的な算出方法は以下の通りです。
LTV = 平均顧客単価 × 収益率 × 購買頻度 × 継続期間
なお、新規顧客獲得の施策について考えるときは、CPO<LTVとなるのが大前提ですが、LTVを最大化するには顧客と長期的な関係を築き、リピートを獲得していくことが欠かせません。そのための施策も考慮に入れると、「CPO+既存顧客維持コスト<LTV」となる必要があります。
新規顧客獲得および既存顧客維持にかかるコストまで含んで粗利ベースのLTVを算出したいときは、以下の計算式を用います。
粗利ベースのLTV=平均顧客単価×収益率×購買頻度×継続期間-(新規顧客獲得コスト+既存顧客維持コスト)
業界業種、業態によって異なるLTVの考え方
| 主な利用シーン / ビジネスモデル | 算出式 | 特徴・ポイント |
| BtoC(リピート通販・サブスクリプション・SaaS型サービス) | LTV = 顧客の平均購入単価 × 粗利率 ÷ 解約率 | 解約率改善がLTV向上のカギ。新規獲得コスト回収を長期的リピートで実現。 |
| BtoB(年間契約・プロジェクト型、大口取引) | LTV = 顧客の年間取引総額 × 粗利率 × 顧客の平均継続年数 | 契約金額や期間が顧客ごとに変動大。年単位での算出が現状把握に有効。 |
| 売上ベースでシンプルに算出したい場合 | LTV = 顧客の平均購入単価 × 平均購入回数 | 粗利を考慮せず売上ベースで評価。短期的なLTV算出に向く。 |
| リピート通販・サブスクリプション・SaaS型サービス | LTV = 顧客の平均購入単価 × 購入頻度 × 平均契約期間 | 契約期間や利用継続度を考慮し、売上ベースでの継続的なLTVを把握可能。 |
| リピートが少ない商材(例:単発型、高単価商品) | (特殊ケース)CPOを小さく抑え、1回購入で回収 | サポート・メンテナンス提供などで関係を維持し、次回購入へつなげる戦略も重要。 |
LTVには、前述の基本の式以外にも算出方法があります。CPOの回収とLTVの向上はどんな企業にとっても重要ですが、LTVに大きく影響する要素は、企業の業界業種、業態によって異なります。そのため、前述の式以外の計算式を使ったほうがより正確なLTVを算出できる場合もあるのです。
たとえば、主にBtoCのリピート通販やサブスクリプション、SaaS型サービスなどのビジネスモデルは、新規獲得に大きなコストをかけ、顧客と長期的な関係を築いてリピートを重ねてもらうことでコストを回収するのが基本です。
この場合、LTV向上には解約率の改善が大きく影響するため、LTV算出に「LTV = 顧客の平均購入単価 × 粗利率 ÷ 解約率」という計算式がよく使われます。
あるいは主にBtoB企業で、年間契約やプロジェクトごとの契約が多い、取引金額が大きい、顧客によって取引の金額や期間が大きく変動するといったビジネスにおいては、LTVに影響する要素を年単位で区切ったほうが現状や変化を把握しやすいです。
この場合、LTV算出には「LTV = 顧客の年間取引総額 × 粗利率 × 顧客の平均継続年数」という計算式が使われます。
この他、売上ベースでLTVを算出したい場合には、「LTV = 顧客の平均購入単価 × 平均購入回数」という計算式を使うケースが多いです。同じく売上ベースで、リピート通販やサブスクリプション、SaaS型サービスの場合には「LTV = 顧客の平均購入単価 × 購入頻度 × 平均契約期間」という計算式も使われます。
また、リピート購入が発生しにくい商材は、CPOをできるだけ小さくして、1度の購入でコストを回収する必要があります。ただし、高単価な商材などは、サポートやメンテナンスなどで顧客との関係性を維持して、長期的に次の購入につなげることでLTV向上を狙う戦略も有効です。
限界CPO
| ビジネスモデル | 限界CPOの算出式 | 含めるコスト範囲 | ポイント |
| BtoC(サブスク・通販・SaaS) | 限界CPO = 粗利ベースLTV −(1人あたりの維持コスト) | ・商品原価 ・物流費(配送・梱包) ・決済手数料 ・CS対応費用(サポートセンター、人件費の按分) ・システム利用料(EC/サブスク管理、サーバー費) | 解約率や継続期間が大きな影響。 サブスクでは「1顧客あたりの月次維持コスト」を入れると精緻化できる。 |
| BtoB(年間契約・プロジェクト型、大口取引) | 限界CPO = 粗利ベースLTV −(1顧客あたりの提供コスト) | ・プロジェクト遂行の原価(人件費、外注費) ・契約維持コスト(アカウント管理、人件費) ・ サービス提供に伴う固定費(サーバー、ライセンス) ・導入・オンボーディング費用 | 顧客ごとに契約金額が大きく変動するため「総コスト÷総顧客数」よりも顧客別に積み上げで算出するのが現実的。 |
限界CPOとは、注文1件を獲得するためにかけられるコストの上限です。これを超えると赤字になるという指標が、限界CPOです。
限界CPOは、以下の計算式で算出できます。
限界CPO=粗利ベースLTVー(対象施策の実施コストを除く総コスト/総顧客数)
この式では、ここまでにCPOを回収したいという期間における数値をあてはめます。そのため、限界CPOは投資の回収サイクルとLTVによって変動します。
前述の通り、LTVについての考え方は業界業種や業態によって異なるため、自社のビジネスや商材に合ったLTVの算出と対象期間の設定を行った上で、限界CPOを算出しましょう。
CPO・LTVから考える投資回収サイクルの具体例
CPO・LTVの目安となる数値は、企業の業界・業種・業態や規模、商材などによってかなり幅があります。ただ、どんな企業にも共通するのが、事業を成長させるためにはCPOを回収した上でLTVの最大化するのが重要ということです。
具体的に、CPO・LTVを算出した上で、LTVの最大化のためにどのようなことができるのか、以下に2つの例を紹介します。
1.WebスクールビジネスのCPO回収とLTV最大化

まずは、Webスクールを商材とする企業を例に、CPO(顧客獲得単価)の回収とLTV(顧客生涯価値)の最大化を考えてみましょう。
ここでは、以下の条件のもとCPOを設計していきます。
- 商材:Webスクール(3か月コース)
- 価格:50万円
- 顧客あたりの提供コスト:20万円(人件費・教材・運営費など)
- 利益(粗利):30万円
- 収益率:60%
- 購入回数:1回(単発)
- 継続期間:3か月
限界CPOの算出方法
今回のケースでは、粗利ベースのLTV(=限界CPO)は以下のように計算されます。
| 粗利ベースのLTV(=限界CPO) = 平均顧客単価 × 収益率 × 購買頻度 = 50万円 × 60% × 1回 = 30万円(3か月) |
つまり、1人の顧客から3か月間で得られる利益は30万円です。
このビジネスは「単発販売型」なので、リピート購入は発生しません。そのため、限界CPOは粗利ベースLTV(30万円)以内に収める必要があります。CPOが増えるほど利益は減るので、目標とする利益を残せるようにCPOを調整しましょう。
3か月間で完結するサービスなら、CPOも3か月以内に回収できる設計にすることが大切です。また、分割払いで売上が分散しても、期間内に広告費を回収できる設計が望ましいでしょう。
利益率を改善し、限界CPOを引き上げる施策
粗利ベースLTVが向上すれば、CPOとして投資できる額が大きくなります。それでは、このビジネスモデルで利益を増やしてCPOの投資余力を拡大するには、どうすればいいでしょうか?
有効な施策例として「アフタースクールサポート(継続プラン)」の導入が考えられます。
アフタースクールサポートを追加した場合の全体の収益構造は、以下のとおりです。
| 項目 | 内容 |
| サポート期間 | 2年間 |
| 料金 | 月額1万円(24か月)=24万円 |
| 提供コスト | 2万2,000万円(2年間合計) |
| 収益率 | 約70%(Webスクール+サポート合計) |
この場合のLTVは、以下のように再計算できます。
| LTV = (Webスクール50万円 + サポート24万円) × 収益率70% = 74万円 × 70% = 約51万8,000万円(2年3か月) |
アップセルを導入することで、粗利ベースLTVが30万円から約52万円まで向上しました。このように、リピート購入が発生しない商材であっても、CPOとして投資できる金額の上限を拡大することは可能なのです。
2.EC物販のLTVと限界CPOからの投資回収期間算出

次は、EC物販を行う企業のマーケティング施策立案を想定してみましょう。
さまざまな商品を扱うEC物販の場合、収益率は商品によって大きく異なるため、今回は売上ベースでLTVを計算します。
| LTV = 顧客の平均購入単価 × 平均購入回数 |
売上ベースのLTVの場合、そこには商品を販売するためにかかるさまざまな費用が含まれるため、それを踏まえて利益が残るようCPOを考えなければいけません。また、年間の施策計画を立てやすくするために、1年間のスパンを想定します。
ここでは、以下の条件のもと限界CPOを設計していきましょう。
- 平均購入単価:2万5,000円
- 1年以内に3回以上購入するユーザーの割合:18%
- 3回以上購入したユーザーの継続率:55%
- 粗利率:55%
- 販売にかかるコスト(合計32%)
- 物流費:25%
- 決済手数料:4%
- CS対応費・システム利用料など:3%
※条件は、一般的なEC物販事業の平均的な指標を参考にしています。
期待購入回数
まずは、顧客ごとの購買行動の違いを反映した期待購入回数を算出するために、顧客を3つのグループに分類しましょう。
期待購入回数は「加重平均」で算出します。各グループの「割合 × 購入回数」を計算し、すべて合計することで、グループごとの人数規模を反映した実態に即した平均値が得られます。
| 顧客グループ | 新規顧客全体に占める割合 | 購入回数/年 | 計算式※1 | 貢献度 |
| 3回以上購入 (継続顧客化) | 18% × 55% = 9.9%※2 | 3回 | 0.099 × 3 | 0.297回 |
| 3回以上購入 (非継続) | 18% × 45% = 8.1%※3 | 3回 | 0.081 × 3 | 0.243回 |
| 1回のみ購入 | 82%※4 | 1回 | 0.82 × 1 | 0.820回 |
| 合計 | 100% | – | – | 1.36回 |
※2:1年以内に3回以上購入するユーザーの割合 × 継続顧客になる割合
※3:1年以内に3回以上購入するユーザーの割合 × 継続顧客にならない割合(100% – 55%)
※4:100% – 18%(3回以上購入しない、1回のみ購入のユーザー)=82%
今回の計算では、1人あたりの平均購入回数は1.36回ということがわかりました。
【1年回収モデル】限界CPOの算出方法
1年以内に投資を回収する設計にする場合、期待購入回数(1.36回)をもとに、粗利ベースのLTVと限界CPOを算出します。
| 計算手順 | 計算式 |
| ステップ1:売上(売上ベース) | 顧客の平均購入単価 × 平均購入回数 = 2万5,000円 × 1.36回 = 3万4,000円 |
| ステップ2:売上に対する維持コスト | 物流費25%+決済手数料4%+CS対応・システム費3% =合計32% 3万4,000円 × 32% =1万880円 |
| ステップ3:粗利ベースLTV | 売上ベースLTV × 粗利率 = 3万4,000円 × 55% = 1万8,700円 |
| ステップ4:限界CPO | 粗利LTV − 維持コスト = 1万8,700円 − 10,880円 = 7,820円 |
つまり、このEC事業ではCPOが7,820円を超えると赤字になります。1年以内に投資を回収したい場合は、CPOを7,820円以下に抑える必要があります。
【2年回収モデル】限界CPOの算出方法
次に、資金体力があり、2年間で顧客獲得コストを回収するモデルを想定します。
2年目は継続率・リピート率を高めるために10%の値引きを実施する前提です。
| ステップ | 内容 |
| ステップ1:期待購入回数(2年合計) | ・1年目の購入回数:1.36回 ・2年目の継続顧客による追加購入 →継続顧客(18% × 55%)が平均3回購入すると仮定 → 0.18 × 0.55 × 3 =0.297回 合計 1.657回 |
| ステップ2:売上(2年合計) | 期待購入回数 × 平均購入単価 ・1年目:1.36×2万5,000円 = 3万4,000円 ・2年目:0.297×2万5,000円 = 7,425円 合計 4万1,425円(2年間の売上) |
| ステップ3:2年目10%値引き適用 | ・2年目の売上(7,425円)に10%の値引きを適用 → 7,425円 × 90% = 6,683円 ・2年間の実質売上 →1年目の売上+2年目の売上= 3万4,000円+6,683円 = 4万683円 |
| ステップ4:維持コスト(売上比率) | 売上 × 販売コスト = 4万683円 × 32% = 1万3,019円 |
| ステップ5:粗利ベースLTV | 4万683円 × 粗利率55% = 2万2,376円 |
| ステップ6:限界CPO | 粗利ベースLTV − 維持コスト = 2万2,376円 − 1万3,019円 = 9,357円 |
2年スパンで回収する設計に変えることで、投資に使える上限CPOは約9,400円まで拡大します。
このように、投資金額の回収期間が長くなれば、限界CPOが向上する傾向があります。
- どのくらいの期間で予算回収をするのか?
- 新規ユーザー獲得のCPOをいくらに設計するのか?
は各会社によるので、参考までにご確認ください。
LTVを向上させるには、「平均単価を引き上げる」もしくは「平均購入サイクルを増やす施策」が有効です。
平均単価を引き上げるには、セット販売や一定金額以上で割引が適用されるクーポンなどが効果的です。平均購入サイクルを増やすには、定期便やタイムセールなどが効果的と考えられます。
CPOを含むさまざまなコストを考慮した予算獲得の具体例については、以下の記事を参考にしてみてください。
適切な回収サイクルを設定するためのポイント
マーケティング予算投資の適切な回収サイクルを設定するためには、正確かつ最新のデータと他部署との連携が重要です。
そのためのポイントを以下にまとめました。
信頼できるデータを基にする
マーケティング予算投資の適切な回収サイクルを設定するためには、ここまで解説してきた通り、CPOとLTVなどの指標を正確に算出する必要があります。
指標を正確に算出するには、正確なデータを基に計算を行いましょう。
まず、過去に類似の施策を実施した際のデータを参考にします。社内に蓄積されたデータが不十分な場合、自社と同じ業界業種や業態で一般的とされる数値を参考にします。
定期的に振り返りと改善を行う
ビジネスの状況は日々変化します。マーケティング予算投資の回収サイクル設定とそのために算出した指標は、一度算出したものを使いつづけるのではなく、定期的な振り返りと更新が欠かせません。
少なくとも月に1回、指標と実績に大きなずれがないかを確認し、ずれがある場合は原因を分析した上で施策の改善または指標の修正を行います。
マーケ部署だけでなく他部署とも情報を共有する
マーケティング施策の実施にあたっては、どのような指標に基づいてどのような施策を行うのか、計画段階で施策に関係する部署への情報共有を行いましょう。
マーケティング施策の実施は、マーケティング部署だけで完結しないことがほとんどです。たとえば、施策の計画の基となるデータの収集や、注文獲得やその後のリピート獲得における顧客とのやり取りにおいては、営業部やカスタマーサポート(カスタマーサクセス)の部署との連携が不可欠です。
マーケティング部署が何に向けてどう動いているのか他部署にも理解してもらうことで、他部署の協力を得やすくなります。特に、投資回収までに時間がかかる施策は、施策の成果に懸念を抱かれないよう、より丁寧に情報を共有し合うようにしましょう。
まとめ
本記事では、マーケティング予算投資の基本と回収についてCPOとLTVを軸にした具体例を紹介しました。限界CPOを算出し、適切な回収サイクルを設計することで、健全なキャッシュフローを維持しつつLTVを最大化することがマーケティング活動においては重要です。
LIFTを運用するゴンドラでもマーケティング支援を行っており、特に カスタマーエンゲージメント を大切にしています。
カスタマーエンゲージメントとは、顧客との関係性を強化することでロイヤルカスタマーへ育成していく考え方です。私たちは新規顧客の獲得はもちろん、獲得したユーザーに対しても適切なコミュニケーションを行い、LTV最大化につなげることを得意としています。
マーケティング施策の設計や改善に課題を感じている方は、ぜひお気軽にご相談ください。
CONTACT お問い合わせ
WRITING 執筆
加藤 淳平
経理・財務分野において、事業会社と税理士法人での実務経験を持つプロフェッショナル。
事業会社では経理・財務・経営企画分野で、決算業務、予実管理、予算策定、組織再編、J-SOX対応まで幅広く従事。税理士法人では財務・税務支援業務に加え、財務DDや株価算定業務を担当。
日商簿記1級、全経簿記上級の資格を有し、税理士試験(簿記論)合格。理論と実務の両面から、企業の財務・経理課題に対する深い知見を有する。