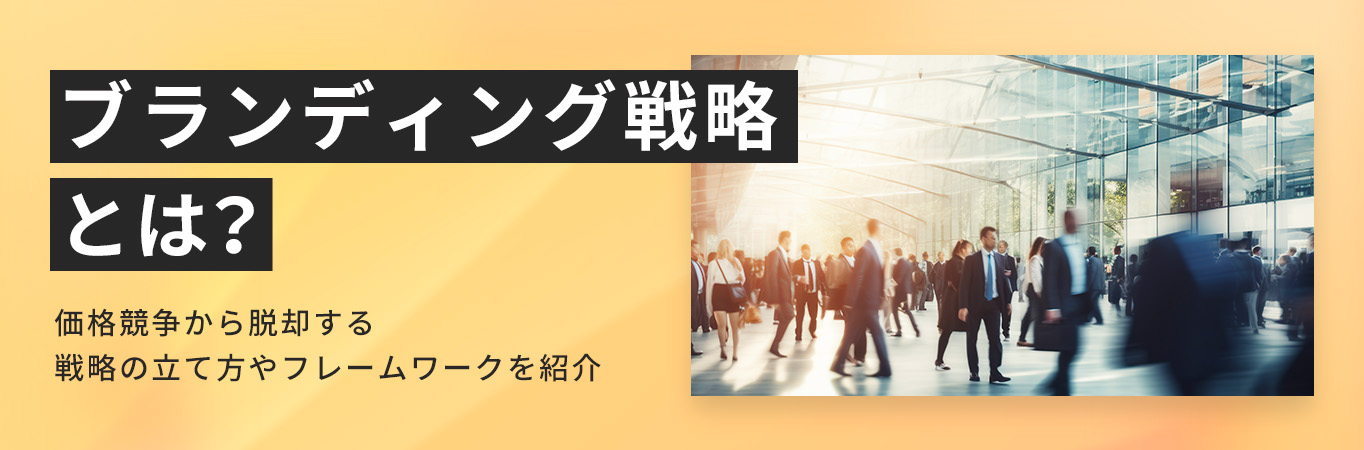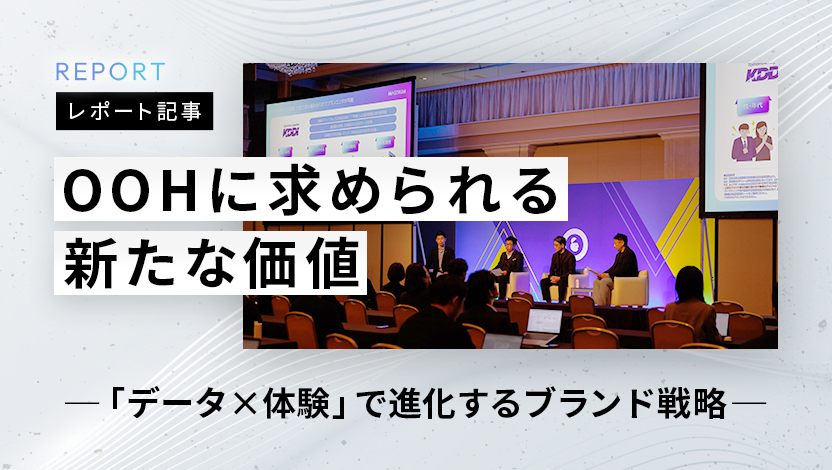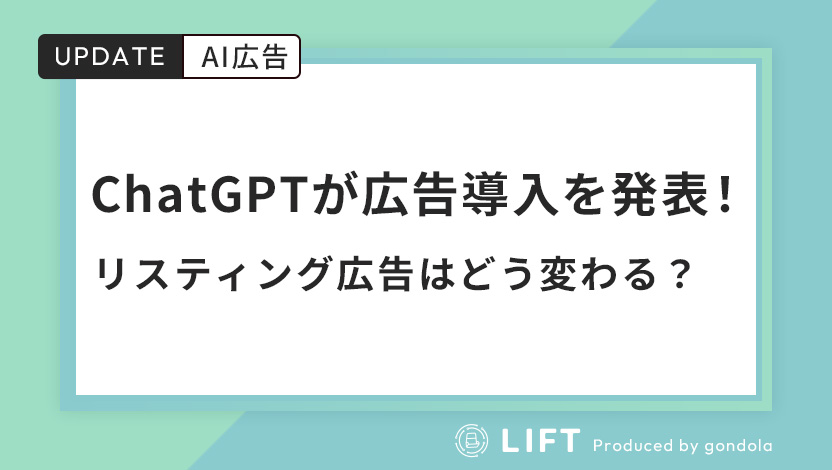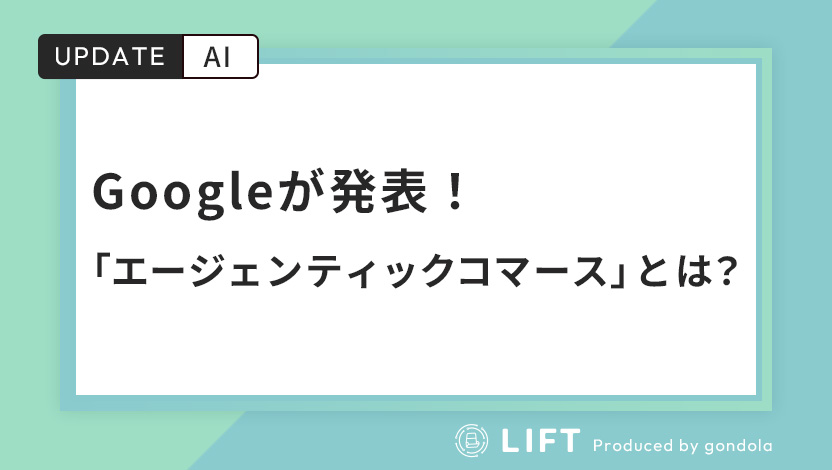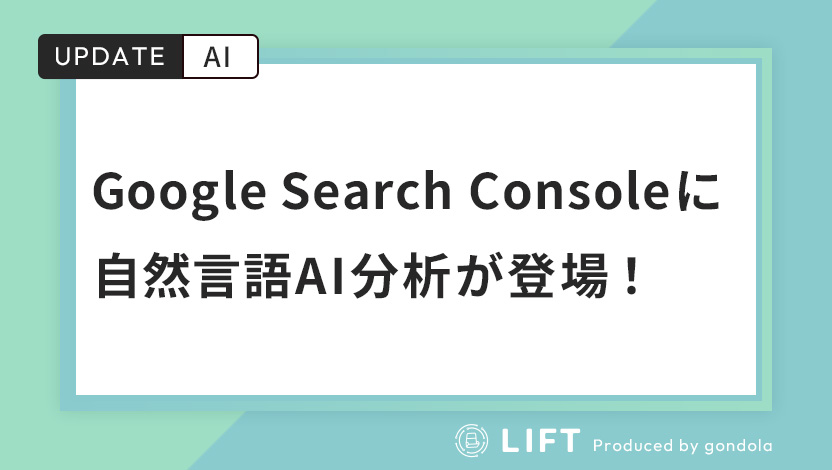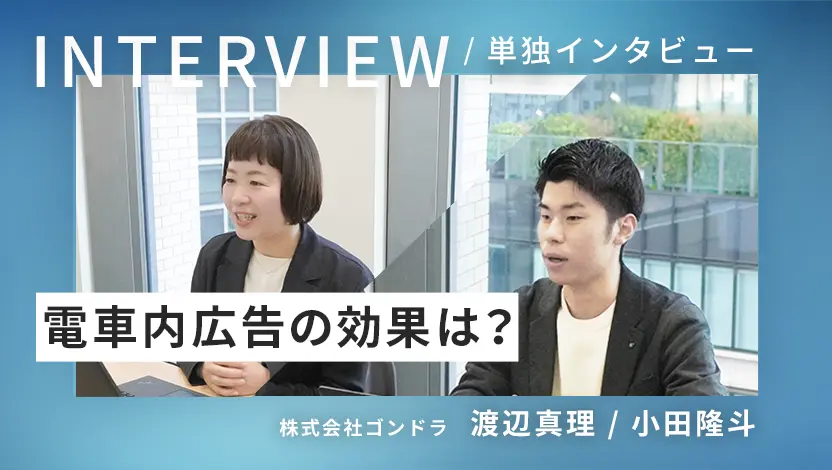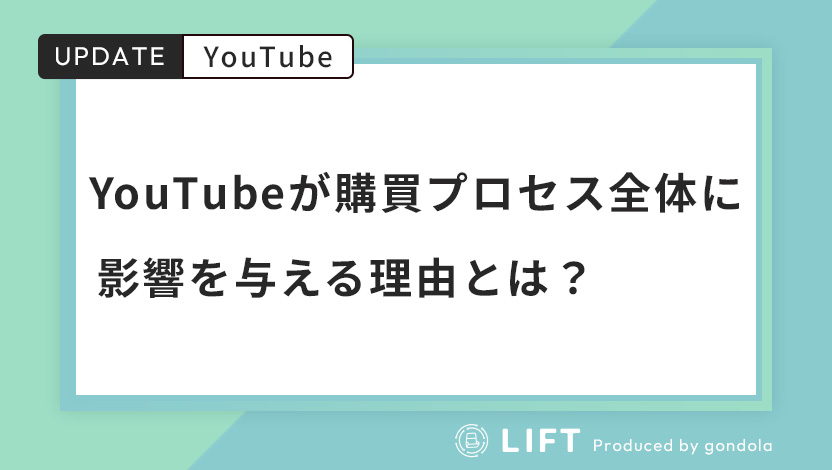ブランディング戦略とは、付加価値を与えることで他社と差別化を図り、顧客に選んでもらえる企業や商品をつくり上げる戦略です。この記事では、ブランディング戦略の立て方や事例、役立つフレームワークについて解説します。ブランディングは、価格競争から脱却して長期的・安定的な利益を得るために欠かせない戦略です。目的別の効果的なブランディング戦略の手法やポイントを知って、自社ならではの魅力を発信していきましょう。
今マーケティングを担当している企業なんですけど、いまいち売上が伸びないんですよね。すっごく品質が高いのに、競合が低価格帯ばかりだから、安い商品にお客さんが流れていってしまって。
価格競争が激しい市場だと、どうしても安い商品にお客さんを取られがちだよねぇ。ブランディング戦略はうまくいっているの?
ブランディング戦略……?今のところ、まだチャレンジしていない取り組みかもしれないです……!
INDEX目次
ブランディング戦略とは
ブランディング戦略は、自社商品や企業をどのように顧客から見られたいのかを決め、その内容の実現を目指すための戦略や取り組みです。ブランディング戦略を立てることで、競合他社との差別化やロイヤルティ(愛着心)の向上を目指せます。
まずは、企業の生き残りに不可欠なブランディング戦略の概要を説明します。
- ブランディング戦略を簡単にいうと?
- ブランディング戦略が重要な理由
- ブランディング戦略と関連用語の違い
上記3項目についてみていきましょう。
ブランディング戦略を簡単にいうと?
ブランディング戦略とは、企業や自社のブランドに独自の付加価値を与えて競合他社と差別化し、顧客に選ばれやすくするための戦略です。顧客にどのような企業・商品だと思ってもらいたいのかを明確化し、その実現のためにさまざまな取り組みを行います。
ブランディング戦略に成功している代表的な企業として、「オリエンタルランド」が挙げられます。東京ディズニーリゾートの施設運営を行うオリエンタルランドは、エンターテインメントの最高峰として世界中から高い評価を得ている企業です。
「あそこに行けば、質の高い接客と感動体験を提供してもらえる」と世界中の人々に認識されることで、熱狂的なファンの獲得に成功。顧客だけではなく従業員へのブランディングも徹底しており、採用活動や高品質なサービス提供につなげています。
このように、ブランディング戦略は自社や商材の価値を高める効果の高い取り組みです。ブランディング戦略に成功すれば競合他社と差別化でき、価格競争から脱却しやすくなります。
ブランディング戦略が重要な理由
ブランディング戦略は、市場での生き残りや利益の向上に欠かせない取り組みです。特に、中小企業やスタートアップ企業にとっては、企業存続に直結する重要な施策であるといえます。
近年、技術の発達や市場の活性化により、商品・サービスの品質や機能に差が生まれにくくなる「コモディティ化」が進んできました。コモディティ化が進めば、「似た機能の商品なら安いほうを選ぼう」と考える消費者が増えて、価格競争が生まれやすくなります。その影響で、現代の市場では競合他社との差別化が難しくなっているのです。
単に安い商品を提供するだけでは企業の利益は上がりませんし、自社より価格が安くてネームバリューの高い企業が登場すれば、すぐに顧客を取られてしまいます。このような状況に陥ることを防ぐには、ブランディング戦略で独自の価値を提供することが大切なのです。
「この企業はサービス品質が優れている」「独自の世界観が好き」など、自社ならではの価値を提供できれば、価格以外の購買動機を与えられます。その結果、多少値段が高くても顧客に選んでもらえるようになり、価格競争から脱却できる可能性が高まるのです。
ブランディング戦略と関連用語の違い
ブランディング戦略と関連する用語として「ブランド戦略」と「マーケティング戦略」があります。
各用語には、どのような意味があるのでしょうか。ここでは、ブランディング戦略と関連用語の違いを紹介します。
ブランディング戦略とブランド戦略の違い
ブランド戦略とは、自社商材をどのように「ブランド」として作っていくのかを考える取り組みです。顧客に抱いてほしい企業や商品に対する評価・イメージを決定する活動が該当します。
一方でブランディング戦略は、ブランドを消費者に認知させ、競争優位性の確立や売上向上を目指す活動です。自社製品に魅力を感じてもらえるようにメッセージを発信したり、ロゴやキャッチコピーを制作したりと、ブランド認知のためのさまざまな取り組みが含まれます。
ブランディング戦略とブランド戦略は、明確に区別されているわけではありません。しかし、「確立したブランドを浸透させていく過程としてブランディング戦略がある」と考えられることが一般的です。
ブランディング戦略とマーケティング戦略の違い
マーケティング戦略とは、商品やサービスが売れる仕組み・市場を作って、消費者に購入してもらうことを目指す活動全般です。商品を売るための総合的な戦略であり、そのなかにはブランディング戦略も含まれます。
一方でブランディング戦略は、企業や商品が持つ価値や独自性を知ってもらうための取り組みです。それぞれは密接に関係しており、ブランディング戦略の成功は、そのままマーケティング戦略の成功に直結します。
簡単にいうと「うちの商品は、競合にはないこんな価値を提供できます」ってみんなに伝えて、選んでもらうための活動がブランディング戦略かな。
なるほどぉ!自社にしかない価値を提案できれば、価格が安くて機能が似ている商品と大きく差別化できるんですね。ブランディング戦略、興味があります!
おっ、じゃあ詳しく教えちゃおうかな。ブランディング戦略には、他にもたくさんのメリットがあるんだよ。反対に、デメリットもあるんだけどね。
ブランディング戦略のメリット・デメリット
ブランディング戦略には多くのメリットがありますが、デメリットもあるため注意が必要です。
ここでは、ブランディング戦略に取り組む企業が押さえておきたいメリット・デメリットを詳しくみていきましょう。
ブランディング戦略のメリット
ブランディング戦略のメリットは、次の4つです。
- 競合他社と差別化できる
- 認知拡大につながる
- ファンを獲得できる
- ステークホルダーへのアピールになる
各メリットについて説明します。
競合他社と差別化できる
ブランディング戦略は、競合他社との差別化に効果的です。
同じような機能の商品がいくつもある場合、どうしても顧客は安いほうへ流れていきがちです。しかし、そのなかで品質やデザイン、保証などが優れているものがあれば、多少価格が高くてもプラスの価値を提供してくれる商品を選択する人が増えます。
現時点で市場をシェアしているブランドや商品がある場合でも、ブランディング戦略で差別化に成功すれば、自社を選択する顧客を一気に増やせる可能性があるでしょう。
認知拡大につながる
ブランディング戦略は、認知拡大にも効果的です。
商品・サービスの品質が高ければイメージアップにつながり、消費者の間で話題になったり情報をシェアしてもらえたりする可能性が高まります。その結果、高額な広告費をかけなくても多くの人に自社を知ってもらえる機会が増えるのです。
ファンを獲得できる
ブランディング戦略には、ファンを獲得する効果もあります。商品やサービスが高い商品は顧客の心を強く掴み、継続利用や愛着心の育成を促してくれます。
ファンが増えれば顧客離れを防げますし、価格にかかわらずリピート購入してくれる人を増やすことが可能です。熱狂的なファンは、情報発信を通じて新規顧客を呼び込んでくれる広告塔になってくれる可能性も秘めています。
ステークホルダーへのアピールになる
ブランディング戦略で企業や商品のよい面を周知できれば、ステークホルダーへのアピールになります。
ステークホルダーへのアピールは、企業経営に多くのメリットをもたらします。例えば、資金調達を有利に進めやすくなったり投資家から信頼を獲得できたりと、ビジネスチャンスを広げる足がかりになるかもしれません。転職・就職希望者が増え、優秀な人材の確保につながることも考えられます。
またブランディング戦略は、社内の人間に対しても効果的です。従業員のエンゲージメントやモチベーションが向上すれば、よりよい商品・サービスが提供できるようになるでしょう。
ブランディング戦略のデメリット
ブランディング戦略のデメリットは、次の3つです。
- 時間やコストがかかる
- 社員や顧客が離れていく可能性もある
- ブランドイメージを簡単に変更できない
どのようなことなのか、詳しくみていきましょう。
時間やコストがかかる
ブランディング戦略には、長期的な取り組みが不可欠です。そのため、多くの時間やコストをかけて実施する必要があります。
いくら魅力的な商品・サービスでも、「うちの商品はここが強みです」と企業がアピールするだけでは消費者に納得してもらうことはできません。さまざまな取り組みや実績の積み重ねを通して、根気強く魅力を浸透させていく必要があります。
社員や顧客が離れていく可能性もある
ブランディング戦略は、既存の社員や顧客が離れていく原因になることがあります。この現象は、「社員や顧客が抱いているブランドイメージ」と「企業が確立したいブランディング」が乖離しているときに起きるため注意が必要です。
一方的なブランディング戦略で企業の価値観を押し付けると、既存ファンの心は離れていってしまいます。ブランディング戦略に取り組むときは、浸透させたいブランドイメージと顧客ニーズがマッチしているかどうかを確認することが重要です。
ブランドイメージを簡単に変更できない
ブランディング戦略で浸透させたブランドイメージは、簡単には変更できません。
例えば、1皿100円で提供していた回転寿司チェーン店があるとしましょう。このチェーン店が時代にあわせてブランドの方向性を変更する「リブランディング」を行い、1皿500円以上の価格設定にしたとします。もちろん高級寿司に対するニーズは一定数ありますが、もともとのブランドを知っていた消費者からは「品質に不安がある」「前のほうが行きやすかった」と受け入れてもらえないかもしれません。
リブランディングが成功するケースは、非常に稀です。そのためブランディング戦略は、長期的な影響を考慮したうえで取り組む必要があります。
なるほど……。ブランディング戦略って、しっかりと計画を立てて慎重に進めていかないといけないんですね。
そうだね。ブランディングって、やり直しがききにくいから難しいんだよね。ブランドを浸透させるには、時間もお金もかかるし。
そもそも、ブランディング戦略で重要になるブランドの浸透って、どうやって実現すればよいのでしょうか。
ブランディング戦略の具体的な手法
ブランディング戦略には、大きく分けると以下の2つの種類があります。
- アウターブランディング
- インナーブランディング
各種類の役割と具体的な手法について詳しくみていきましょう。
アウターブランディング
アウターブランディングとは、社外の顧客や外部のステークホルダーに向けたブランディング戦略です。企業やサービスに対するイメージをコントロールし、認知拡大や売上向上を目指します。
アウターブランディングには、次のような手法が有効です。
- 企業ブランディング
- 商品ブランディング
- サービスブランディング
それぞれの手法がどのようなものなのか説明します。
企業ブランディング
企業ブランディングとは、企業そのものをブランディングする手法です。
企業ブランディングに成功している企業として、Apple社が挙げられます。Apple社自体がブランド化されているので、ファンはスマートフォンだけではなくPCや時計、イヤフォンなどあらゆる商材に高い価値を感じるのです。
企業ブランディングに取り組むときは、企業の理念や価値観を顧客に伝え、共感や応援してくれるファンを獲得する必要があります。
- 環境保護・社会貢献への取り組みのアピール
- オウンドメディアを通じた情報提供
- ストーリーテリングを通じた共感・応援の獲得
上記のような取り組みで、企業自体に魅力を感じてもらうことが大切です。
商品ブランディング
商品ブランディングは、特定の商品をブランディングする手法です。
例えば、掃除機と聞いてどのような商品を思い浮かべますか?人によってさまざまかもしれませんが、多くの方がダイソンの掃除機が頭をよぎったのではないのでしょうか。このように「〇〇といえば〇〇社」と、商品自体をひとつのブランドにする取り組みが商品ブランディングなのです。
商品ブランディングでは、商品そのものが持つ競争優位性を高められるだけではなく、他の商品への波及効果を得ることも可能です。
ダイソンの場合、掃除機で確立したブランドのイメージを活用して、扇風機やドライヤーの開発・販売にも着手。「ダイソンなら安心」「機能性が高そう」と、掃除機以外の商品も多くの顧客に支持されています。
商品ブランディングを行うときの取り組みとしては、次のような施策が有効です。
- インパクトのある商品名にする
- パッケージやデザインを工夫する
- 品質や価格で差別化を図る
- 魅力的なキャッチコピーを作る
- 広告やメディアを通じて継続的にアピールする
大切なのは商品の優劣ではなく、独自性をアピールすることです。既存商品の名称やデザインを変更する「リブランディング」を行うだけでも、商品ブランディング効果を得られる可能性があります。
サービスブランディング
サービスブランディングは、サービスやその提供者をブランディングする方法です。顧客体験に焦点を当てて、信頼性や価値を提供します。
サービスブランディングに成功した企業の代表的な例として、スターバックスが挙げられます。スターバックスの飲食物は決して安くありませんが、スタッフの接客や店内の空間を心地よく感じてファンになるユーザーは決して少なくありません。
サービスブランディングはサービス業や飲食業で重要になる取り組みですが、その他の業界でも応用することが可能です。
- 専門技術・知識を持つ開発者などの権威性をマーケティングに利用する
- カスタマーサービスの顧客体験を向上させて信頼を獲得する
- イベントや工場見学など、顧客と交流する際の対応品質を向上させる
上記のように、さまざまなタッチポイントにおけるサービス品質の向上を実現できれば、企業ブランディングや商品ブランディングとの相乗効果を狙えるでしょう。
インナーブランディング
インナーブランディングとは、社内の従業員に対するブランディング戦略です。企業ブランドやミッション、価値観などを浸透させることで、ロイヤルティやモチベーション、サービス品質の向上を狙います。
インナーブランディングに成功すれば、従業員が企業や自分の仕事に誇りを持てるようになります。その結果、離職率の低下や業績向上など、安定した企業経営の基盤を固めやすくなるのです。
インナーブランディングに効果的な施策の一例として、次のようなものが挙げられます。
- 社内報の発行
- 社内研修の実施
- ワークショップ・イベントの開催
- 上司との定期的な面談
- 積極的なコミュニケーション
そもそも、組織内のメンバーがブランドの理念や価値観を理解していなければ、顧客に対して一貫性のある商品・サービスは提供できません。インナーブランディングは、アウターブランディングの成功に欠かせない取り組みです。
へぇ~。一口にブランディング戦略といっても、いろいろな取り組みがあるんですね。これだけ手法がたくさんあると、何から手をつければいいのかわからなくなってしまいそうですっ。
全部一気に取り組む必要はないよ。自社の課題にあわせて、必要な施策を戦略的に取り入れていこうね。
自社の課題にあったブランディング戦略って、どうやって立てればいいのでしょうか?
ブランディング戦略の立て方
ブランディング戦略を立てる手順は、以下のとおりです。
- 自社と競合の情報を整理する
- ターゲットを明らかにする
- ブランドコンセプトを設計する
- ブランドコンセプトを具現化する
- 改善しながら継続する
各プロセスのポイントを詳しくみていきましょう。
自社と競合の情報を整理する
まずは、自社や競合状況を分析して市場の現状を把握する必要があります。
整理しておきたい具体的な情報としては、次のようなものが挙げられます。
- 歴史や企業文化
- MVV(ミッション・ビジョン・バリュー)
- 経営資源
- 独自性・強み
- 課題・弱み
- 市場での立ち位置
- 業界におけるシェア率
- マーケティング戦略
- 品質や価格帯などの商品概要
また、自社や市場を取り巻く環境についても把握しておきましょう。
- 市場規模
- 業界の流行り
- 政治や法律の影響
- 成長率
- 最新技術
- 経済の状況
ここで分析した内容は、ブランディング戦略の基礎となる重要な材料です。先入観や主観を排除して、客観的かつ正確な情報を集めてください。
ただし、自社だけで収集できる情報には限界があります。アンケートやコミュニケーションなどを通じて、顧客が感じている企業の強みや課題についても明確にしていきましょう。
ターゲットを明らかにする
次に、自社商材にマッチするターゲットを明らかにします。既存顧客の傾向から分析するほか、自社商材が満たせる新たなニーズや見落としていた顧客層を発見することも大切です。
ターゲットを選定するときは、ペルソナ設計が有効です。ターゲット像をより具体的にすることで、判断軸や抱えている課題、行動に応じた最適なタッチポイントを整理できます。
ポイントは、広く浅くではなく狭く深くターゲットを設定していくことです。幅広い層にそこそこ支持されることを目指していては、他社との差別化はできません。自社や商品に強く魅力を感じてくれる一部の層を狙うことが、ブランディング戦略成功の秘訣です。
ブランドコンセプトを設計する
ターゲットを設定したら、その人たちに支持されるブランドコンセプトを設計しましょう。
この際に決めておきたい項目の一例として、次のようなものがあります。
- 差別化ポイントや自社の立ち位置(ポジショニング)
- 顧客に対して約束する品質・機能・価値(ブランドプロミス)
- ブランドの基本的な価値観や信念(コアメッセージ)
- ブランドを象徴する視覚的・定義的な要素(ブランドアイデンティティ)
ブランドコンセプトを設計するときは、世界観に一貫性を持たせましょう。また、それぞれをしっかりと言語化し、誰が見ても理解できるようにしておかなければいけません。
設計したコンセプトは、社内に浸透させて共通理解を得ておきましょう。従業員一人ひとりの発言や発信はブランドイメージに強く影響するため、アウターブランディングを実施する前にインナーブランディングを済ませておく必要があります。
ブランドコンセプトを具現化する
消費者にブランドを浸透させていくために、ブランドコンセプトの具現化を行いましょう。
まずは、設計したコンセプトにのっとって「抽象メディア」を制作します。抽象メディアとは、ロゴやキャッチコピーなどブランドコンセプトを象徴する要素です。抽象メディアは、ブランディング戦略のさまざまなシーンで活用されるので、慎重に作り込む必要があります。
次に、抽象メディアを「可視メディア」に落とし込みましょう。可視メディアは、Webサイトや商品パッケージ、看板、グッズなど、顧客が直接手に取ったり目にしたりするものを指します。別名「ブランディングツール」と呼ばれることもあります。
また、体験を提供することもブランドコンセプトの浸透には重要です。情報提供やイベントの開催、接客など、さまざまな体験を通じてブランドコンセプトを表現していきましょう。
この際、ガイドラインを設定してブランドイメージや世界観の管理・維持を徹底することが大切です。ターゲットやブランドコンセプトによって必要な施策は異なるので、自社に必要な情報発信やタッチポイントの設定を行うことが重要です。
改善しながら継続する
ブランディング戦略を成功に導くには、長期的な取り組みが不可欠です。効果測定と改善を繰り返しながら、戦略の実践を継続しましょう。
ただし、ブランディングの成果を測定するときは、成約数やPV数のように明確なデータを得ることが困難です。信頼感や好感度などの抽象的な概念を数値化しなければいけないので、複数の指標を組み合わせながら効果測定する必要があります。
ブランディング戦略の効果を測定するときは、次のような指標が有効です。
- 認知度
- 新規接触率
- NSP®(Net Promoter Score)
- DWB(Definitel Would Buy)
- 顧客満足度
- 従業員満足度
また、数値だけを見て判断するのではなく、顧客の意見を吸い上げることも非常に重要です。アンケートや顧客からの意見に耳を傾ければ、ブランディング戦略を成功させるヒントが得られます。
特に重要なのが、自社や競合の情報を整理してブランドコンセプトに反映するプロセスかな。ここで決めたことが企業や商品の長期的なイメージに直結するから、時間をかけてじっくりと行う必要があるよ。
わわわ、情報の整理とかブランドコンセプトの設計とか、難しそうなことばかりです。僕みたいな初心者には、やっぱりできないですよね?
そんなことはないよ。フレームワークに沿って考えていけば、ビギニャー君でもブランディング戦略に挑戦できるはず。
ブランディング戦略に役立つフレームワーク
ブランディング戦略で重要になる情報や思考の整理には、フレームワークが役立ちます。
活用できるフレームワークは無数にありますが、ここでは代表的なものを6つ紹介します。
- SWOT分析
- PEST分析
- 3C分析
- ポジショニングマップ
- カスタマージャーニーマップ
- ブランドの扇
各フレームワークの概要をみていきましょう。
SWOT分析
SWOT分析は、企業の内部環境と外部環境を客観的に分析し、効果的な経営戦略を立てたいときに便利なフレームワークです。市場や競合他社、経済などの「外部環境」と、自社の強みや弱みなどの「内部環境」を整理したうえで、ビジネス戦略や経営資源の最適化を目指します。
SWOT分析で取り扱う具体的な要素は、次の4つです。
- Strength(強み):自社が持つ強み、技術力の強さ、顧客数など
- Weakness(弱み):自社が苦手とすること、できていないこと、競合に劣っていることなど
- Opportunity(機会):ビジネスチャンスとなる環境の変化
- Threat(脅威):自社の強みを打ち消すリスクがある環境変化
なお、各要素を整理したあとは「強み×機会」「強み×脅威」「弱み×機会」「弱み×脅威」を組み合わせる「クロスSWOT分析」を行いましょう。ブランディング戦略の具体的な戦術を考えるヒントになります。
PEST分析
PEST分析は、4つの外的要因から業界を分析して、社会全体の動向を把握するためのフレームワークです。自社のポジションや競争優位性を見極めるときに有効で、中長期的な戦略の立案に役立ちます。
PEST分析で取り扱う具体的な要素は、次の4つです。
- Politics(政治):法律、税制、政権交代など
- Economy(経済):経済状況、為替、株価、景気動向など
- Society(社会):人口動態、構成、流行、世論、教育など
- Technology(技術):技術、特許、インフラ、イノベーションなど
上記の情報を整理すれば、自社にとってのチャンスや脅威の発見につなげられます。外的要因は自社でコントロールできない部分なので、あらかじめ把握してリスク回避やビジネスチャンスの獲得に備えておくことが大切です。
3C分析
3C分析は、自社の経営環境を整理して、ブランドの主要成功要因(KSF:Key Success Factor)を見つけるためのフレームワークです。ターゲットを選定するときやブランドコンセプトを設計するときに役立ちます。
3C分析で取り扱う具体的な要素は、次の3つです。
- 顧客や市場(Consumer):市場規模や成長性、顧客のニーズ、消費行動の傾向など
- 競合(Competitor):競合企業のシェア、競合企業の特徴、業界のポジション、今後予想される行動など
- 自社(Company):企業理念やビジョン、強み、リソース、事業や製品の状況など
3C分析を行うと、ユーザー目線で自社商材や市場を理解できるようになります。自社を取り巻く環境についてよい面と悪い面の両方から分析することで、独自性や生き残るための戦略を考案しやすくなるでしょう。
ポジショニングマップ
ポジショニングマップは、自社のポジション(立ち位置)を明確化するためのフレームワークです。自社ならではの独自性や強み、狙うべき市場、ターゲットを分析できるので、競合他社との差別化ポイントを探すときに役立ってくれます。
ポジショニングマップを作成するときは、次の手順で情報を整理します。
- 競合と自社製品に関する情報を整理する
- 競合と自社のKBFを比較する
- ポジショニングマップの軸を決める
- ポジショニングマップを作成する
- 作成したポジショニングマップから空白の領域や自社の立ち位置を分析する
自社や他社の立ち位置を可視化できる点が、ポジショニングマップの大きな強みです。データや文字だけではなく図を用いて分析を進めるため、新しい発見やひらめきが生まれやすくなります。
カスタマージャーニーマップ
カスタマージャーニーマップは、顧客の感情や購買行動、企業との接点などの顧客体験を図にまとめ、可視化するフレームワークです。「認知」「比較・検討」などのフェーズごとに顧客の心理的変化や行動をまとめ、それぞれにおける課題の発見や施策の策定に役立てます。
カスタマージャーニーマップを利用すれば、「認知段階の人にはこの施策」「購入後にはこの施策」と、各フェーズで必要な施策を整理しやすくなります。
ブランドの扇
ブランドの扇は、ブランドが提供する価値を5段階で決めるフレームワークです。どのようなユーザーに何を提供すべきかを明確化できるので、ブランドアイデンティティの設計に役立ちます。
ブランドの扇では、次の5つの要素について情報を整理します。
- 具体的な事実・特徴:商品、サービス、技術などの特徴
- 機能的価値:ブランドから得られる機能的な価値
- 心理的価値:ブランドから得られる感情的な価値
- ブランドパーソナリティ:ブランドが醸し出す世界観や雰囲気
- ブランドエッセンス:ブランドの総合的な価値と顧客に対する約束
ブランドの扇を作成するときは、現状分析や情報収集、自社の特徴の洗い出しなど多くのプロセスが必要になります。情報を収集・整理する過程で社内の人々を巻き込みながら合意形成を進めると、より深い分析やインナーブランディングにつなげることが可能です。
代表的なフレームワークは、こんな感じかな。いろいろなフレームワークが役立つから、整理したい情報にあわせて他のものもぜひ活用してみてね
は~いっ!枠組みに沿って情報を整理すればいいなら、僕でもできそうですっ!ブランディング戦略、挑戦してみようかな!
おっ!それなら、ブランディング戦略を立てるときのポイントも教えておこうかな。
ブランディング戦略を立てるときのポイント
ブランディング戦略を立てるときは、次のポイントを意識すると効果を得られやすくなります。
- わかりやすいコンセプトにする
- ストーリー性を持たせる
- 消費者の視点に立つ
- イメージダウンに注意する
各項目について深掘りしていきましょう。
わかりやすいコンセプトにする
ブランディング戦略で発信していくコンセプトやメッセージは、とにかくわかりやすくすることが重要です。複雑なコンセプトや難しいメッセージは、一般消費者に理解してもらえない可能性があります。
大切なのは、ターゲットはもちろん、それ以外のどのような消費者にも伝わりやすい独自性を提供することです。差別化を狙って難しい専門用語や技術を盛り込むとユーザーに伝わりにくくなるので、子どもでも理解できる簡単な言葉で表現しましょう。
ストーリー性を持たせる
ブランディング戦略では、消費者から共感を得ることが重要です。商品自体の機能や品質に加えて「感情的なつながり」の構築を目指すと、より顧客の心をしっかりと掴めるようになります。
顧客の心を動かして共感を得るには、ストーリー性を持たせる戦略が有効です。開発の背景や大切にしている価値観などをストーリーとして伝えることで、感情面に強く訴えかけることが可能となります。
消費者の視点に立つ
ブランドコンセプトの設計や価値提供の方法を考えるときは、消費者目線に立つことを意識しましょう。
ブランディング戦略では、顧客のニーズを満たせる価値を提供することが大切です。企業が伝えたいことや、構築したいブランドイメージを一方的に押し付けることは避けましょう。
また、顧客視点に立ってみると、今までとは違うターゲット層やブランドのアピールポイントがみえてくることもあります。SNSやアンケートを活用して顧客の意見を取り入れると、ミスマッチのないブランディング戦略を立案しやすくなるでしょう。
また、ブランディング戦略の実施を開始したあとも、消費者視点に立つことは重要です。積極的に消費者の意見を聞き入れて、より顧客に寄り添った商品・サービスになるよう改善していきましょう。
イメージダウンに注意する
ブランディング戦略の内容によっては、大きなイメージダウンにつながるおそれがある点に注意が必要です。
特に、次のような施策はイメージダウンにつながりやすいため、可能な限り避けることを推奨します。
- 性別や年齢など、対象者を限定しすぎる排他的なキャンペーン
- 既存サービスと大幅に乖離した施策
- 反対意見への安易な迎合によって一貫性が喪失された施策
ブランディング戦略を立てるときは、顧客に与えるイメージや反応を予測しておきましょう。意図せず企業価値を下げる戦略を立てないように、十分注意してください。
わわわ、ブランディング戦略がマイナス効果になってしまうこともあるんですね。気をつけようっと。ところで先輩、ブランディング戦略に成功した企業って、具体的にどんな取り組みをしているんですか?
そうだねぇ。例えば、こんな取り組みでブランディング戦略を成功させた有名企業があるよ。
ブランディング戦略の企業成功事例
ブランディング戦略で高い成果を挙げた企業の事例を2つ紹介します。
とらや
とらやは、羊羹や季節の生菓子を製造・販売する老舗和菓子メーカーです。高品質な和菓子を提供することで、「高級な和菓子店」というイメージをつくり上げてきました。
伝統を大切にするとらやですが、市場の変化に対応するためにインバウンドや若者世代にも支持してもらえるようにリブランディングを実施。和菓子をベースにしつつ、洋菓子風にアレンジした商品を開発しました。
さらに、空港や海外への出店やカフェの展開を通じ、より多くの消費者へ積極的にアプローチ。ターゲット層を広げることに成功し、新しい市場を開拓しました。
星野リゾート
リゾートホテルを運営する星野リゾートは、幅広い顧客ニーズに対応できるサービス提供を通じてブランディング戦略に成功した企業です。
さまざまな顧客層に適したコンセプトのサブブランドを5つ展開し、個々の施設をしっかりとブランド化。顧客は自分にあったブランドを選べるだけではなく、グループ施設全体でのリピートを楽しめるため、飽きずに何度も足を運んでもらうことが可能となっています。
さらに、国内の顧客を大切にする姿勢を貫き、高品質な本物のサービスの提供に尽力。柔軟かつ親身なおもてなしは国内のファン獲得に大きく貢献し、結果的に海外顧客への強いアピールにもつながっています。
事例からもわかるように、ブランディング戦略で大切なのは一貫性や芯を持って取り組むことなんだ。芯となる部分がしっかりとしていれば、中小企業でもブランディング戦略を成功させられる可能性はあるよ。
勉強になりました!ありがとうございます、先輩。さっそく、相談してくれた企業にブランディング戦略を提案してみようと思います!
喜んでもらえるといいね!応援しているよ。
CONTACT お問い合わせ
WRITING 執筆
LIFT編集部
LIFT編集部は、お客様との深いつながりを築くための実践的なカスタマーエンゲージメントのヒントをお届けしています。