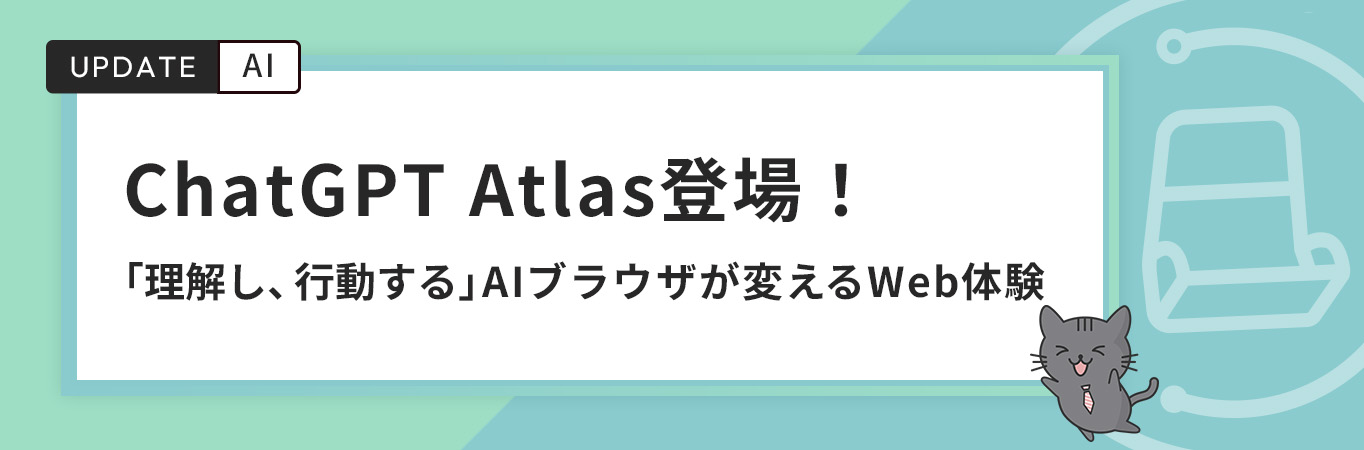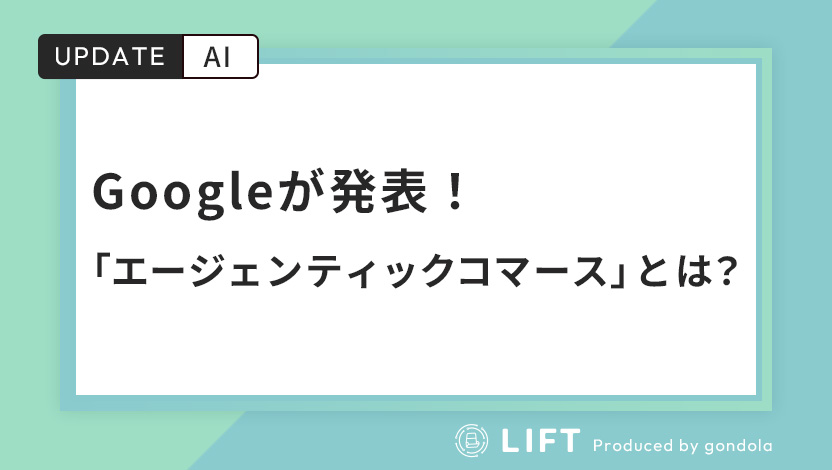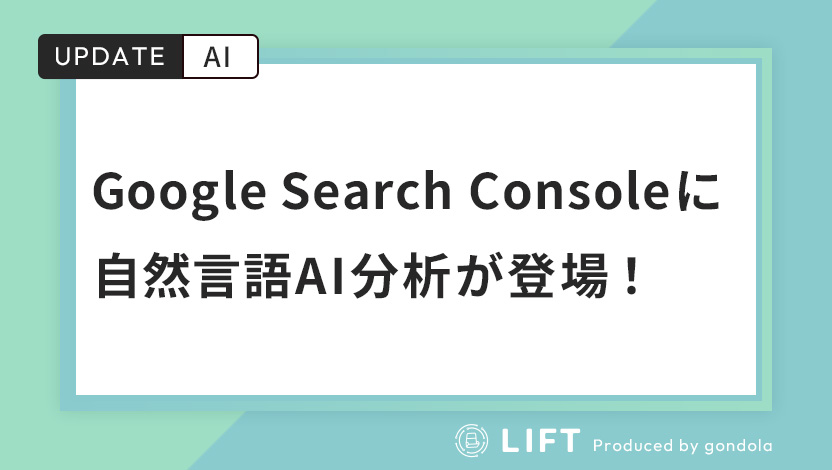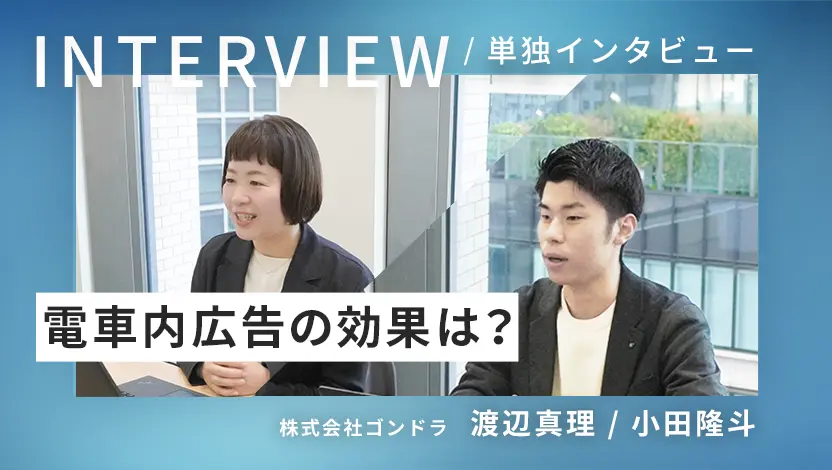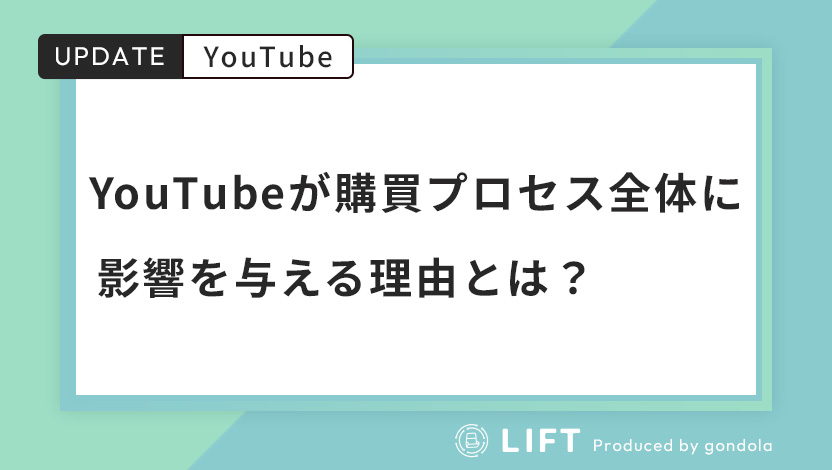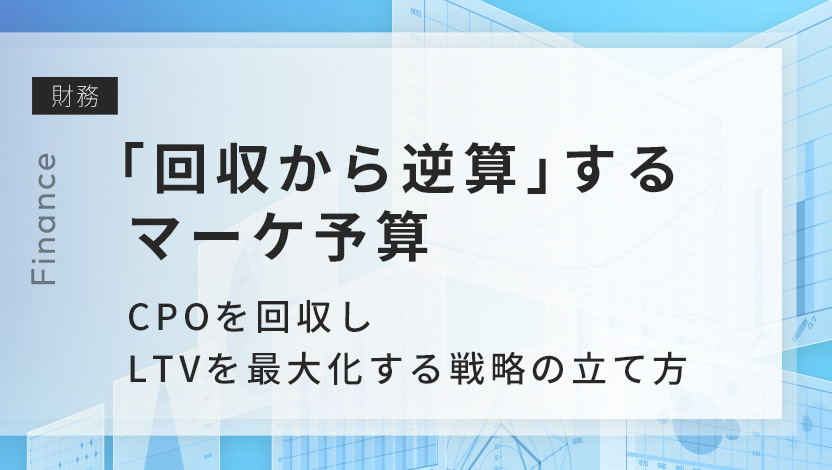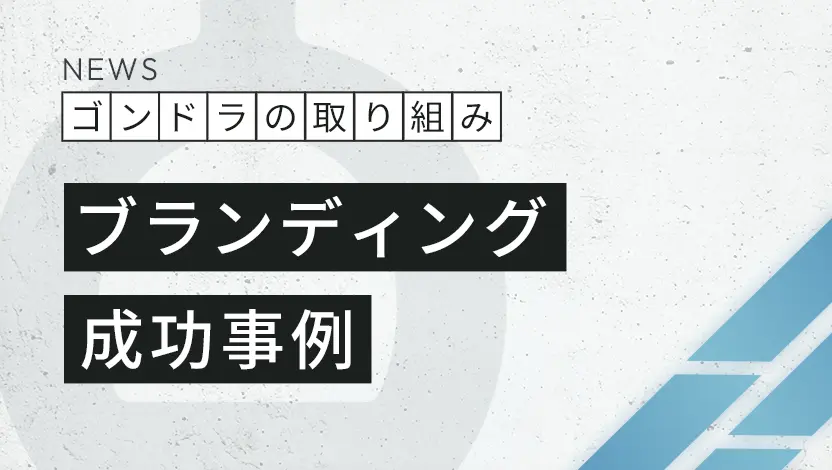OpenAIより、新しいWebブラウザ「ChatGPT Atlas(チャットジーピーティー・アトラス)」がリリースされました。従来のChromeやSafariのようなブラウザが単なる”閲覧ツール”であったのに対して、Atlasは“理解し、行動するAIブラウザ”として設計されています。
本記事では、ChatGPT Atlasの特徴を解説したうえで、マーケティング業務での具体的な活用例を紹介します。
ChatGPT Atlasとは?
ChatGPT Atlasは、ユーザーが閲覧しているページをChatGPTがリアルタイムで理解し、ページ上で質問に答えたり内容を要約したり、作業を自動化したりできるブラウザです。
これまでのブラウザは「情報を表示する窓」の役割しかありませんでした。しかし、Atlasは「情報を理解し、ユーザーの代わりに行動するAIエージェント」へと進化しています。
これにより、ユーザーは検索から分析、実行といった一連の流れを、ブラウザ内でシームレスに行うことが可能となりました。
詳細な機能は、以下のとおりです。
過去を記憶する「ブラウザメモリ」機能
Atlasの最大の特徴は、「ブラウザメモリ」と呼ばれる記憶機能です。ユーザーが過去に訪問したサイトや会話内容を記憶し、その情報を活用してより精度の高いサポートを行います。
例えば、「先週見た求人情報をまとめて面接準備に役立つ業界動向を教えて」と指示したとしましょう。すると、Atlasは閲覧した求人ページを思い出し、それらをもとに自動で分析や要約を行ってくれます。
もちろん、このメモリ機能は完全にユーザーの管理下にあります。履歴を消去すればメモリも同時に削除されますし、一時的にメモリ機能を無効化することも可能です。
つまり、AIが自分の行動を覚えていることへの不安を最小限に抑えながら、利便性を向上させられる仕組みになっているのです。
タスクを代行する「エージェントモード」
「エージェントモード」と呼ばれる新機能にも注目です。これは、ChatGPTがユーザーの代わりにブラウザ操作を行う、”行動するAI”を実現する機能です。
例えば、ユーザーがレシピを入力すると、Atlasがその材料をオンラインストアで自動的に検索し、カートに追加して注文まで完了させられます。他にも、過去のチーム文書を開いて内容を読み上げたり、競合サイトを分析して要点をまとめたりすることも可能です。
つまり、情報収集に加え、実際のタスク遂行までをAIが担えるようになったのです。
安全性への徹底した配慮
もちろん、安全性への配慮も徹底されています。
ChatGPTはブラウザ内で行動する際、金融機関のページや個人情報を扱うサイトでは自動的に動作を制限します。また、ChatGPTが閲覧できるサイトの範囲はユーザー自身がコントロールでき、必要に応じてログアウトモードを利用することも可能です。
デフォルトでは閲覧した内容がモデルのトレーニングに利用されることもなく、オプトイン(自ら同意)しない限り、データがAI学習に使われることはありません。つまり、利便性とプライバシーの両立が図られた設計になっているのです。
提供状況と今後の展開
現在はmacOS向けにリリースされており、Windows、iOS、Android版は順次登場予定です。
将来的にはマルチプロファイル対応や開発者向けSDKの公開も予定されているので、今後は企業や教育機関への導入も見込まれています。
Webマーケティング業務での3つユースケース
ChatGPT Atlasは、Webマーケティング業務を大幅に効率化する可能性を秘めています。
ここでは、実際の業務シーンを想定した具体的な活用例を紹介します。
コンテンツ制作:リサーチから原稿作成まで1画面で完結
これまでの記事制作では、競合記事を複数タブで開き、内容をメモしながらChatGPTで下書きを作成し、ドキュメントツールで編集するという、ツールをまたぐ作業が必要でした。
Atlasを使えば、この業務フローが劇的にシンプルになります。
例えば、検索上位の記事を5〜6個開いた状態で「これらの記事で共通して扱われているトピックと、まだ誰も書いていない切り口を教えて」と指示したとしましょう。すると、ブラウザメモリが全ページの内容を記憶し、包括的な分析を返してくれるのです。
さらに、そのまま「この切り口で3000文字の記事構成を作って」と続ければ、競合分析を踏まえた独自性のある記事が完成します。
SNS投稿を作成するときも、業界ニュースを確認しながら「今週話題のトピックで、うちのターゲット層に刺さる投稿案を3つ出して」と指示すれば、情報収集から企画、執筆まで一気に完結できます。
広告運用:レポート画面を見ながら改善案をその場で策定
Atlasは、広告運用業務も効率化してくれます。
例えば、Google広告の管理画面を開いている状態で、「このキャンペーンのCPAが高い理由と、具体的な改善施策を3つ教えて」と指示します。すると、Atlasは画面上のデータをリアルタイムで読み取り、クリック率やコンバージョン率、ターゲティング設定などを総合的に分析して改善案を提示してくれるのです。
これまでは、レポートをスプレッドシートにエクスポートし、データを整理してから分析するという手間がかかっていました。しかし、Atlasなら管理画面を見ながら対話するだけで、データ分析から施策立案までがその場で完了します。
さらに、「先月と比較して、どこが改善してどこが悪化しているか教えて」といった時系列分析も可能です。ブラウザが過去に見たレポートを覚えているため、その場ですぐ回答を得られます。
競合・市場調査:複数サイトを横断した戦略分析
競合・市場調査も、Atlasが得意とする業務です。
例えば、新規クライアントとのミーティング前の競合調査を行うときに活用してみましょう。
競合5社のWebサイトを順番に訪問してから「これら5社のサービス特徴、価格帯、ターゲット層を比較表にまとめて。そのうえで、うちのクライアントが取るべき差別化戦略を3つ提案して」と指示します。
Atlasは訪問した全サイトの情報を記憶しているため、自分でメモを取る必要がありません。エージェントモードを使えば、「各社のSNSフォロワー数も調べて追加して」といった追加調査も自動で実行してくれます。
また、自社サイトの改善でも活用することが可能です。ランディングページをGoogle Analyticsで分析しながら「このLPの離脱率が高い理由を、アクセス解析データとLP内容の両方から分析して」と指示すれば、データと実際のコンテンツを紐付けた具体的な改善提案が得られます。
マルチタスクから「1画面完結」へ
ここまでに紹介した活用例に共通するのは、「複数ツールを行き来する手間の削減」と「文脈を保ったまま作業が進められる効率性」です。
今までは、ブラウザやChatGPT、ドキュメントツールといった複数のツールを行き来し、その都度情報をコピー&ペーストしたり、文脈を説明し直したりする必要がありました。Atlasは、この「ツール間の断絶」を解消することが可能です。
検索、分析、執筆、データ抽出、競合調査といった作業が画面内でシームレスにつながれば、Webマーケティング業務の効率は大きく向上します。思考を中断されずに深く掘り下げられるようになることで、時短だけではなく、戦略の質や施策のクリエイティビティ向上にもつながるでしょう。
Atlasの登場は、私たちの「働き方の標準」が変わる転換点になるかもしれません。AIとの協働を前提とした新しいワークフローを構築することが、これからのマーケターに求められるスキルとなっていくはずです。
AI技術の進化を追いながら、ユーザーにとって本当に価値のある体験を提供するための広告戦略を構築していきましょう。
CONTACT お問い合わせ
WRITING 執筆
LIFT編集部
LIFT編集部は、お客様との深いつながりを築くための実践的なカスタマーエンゲージメントのヒントをお届けしています。