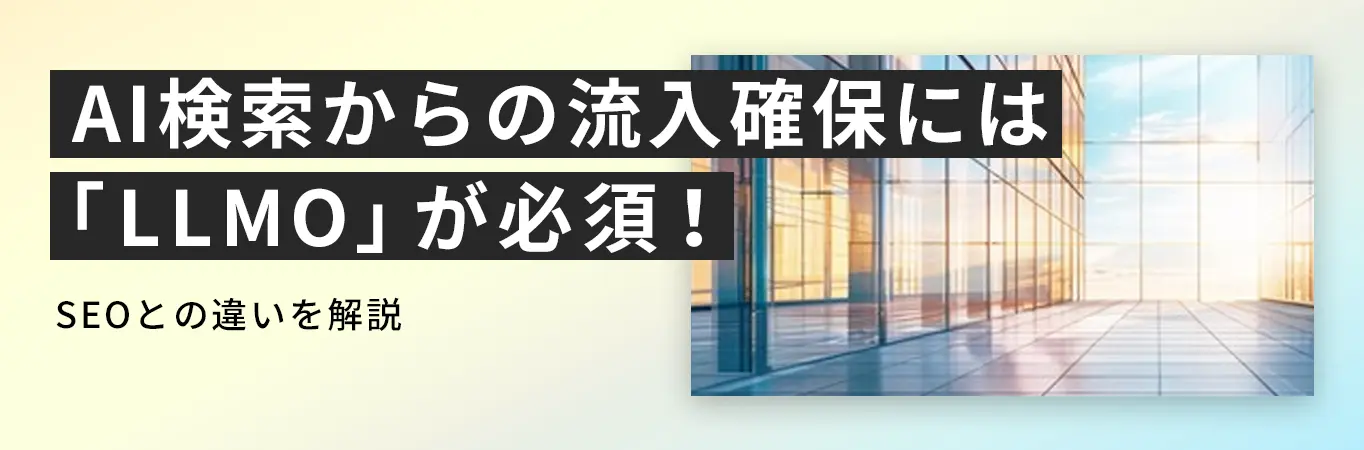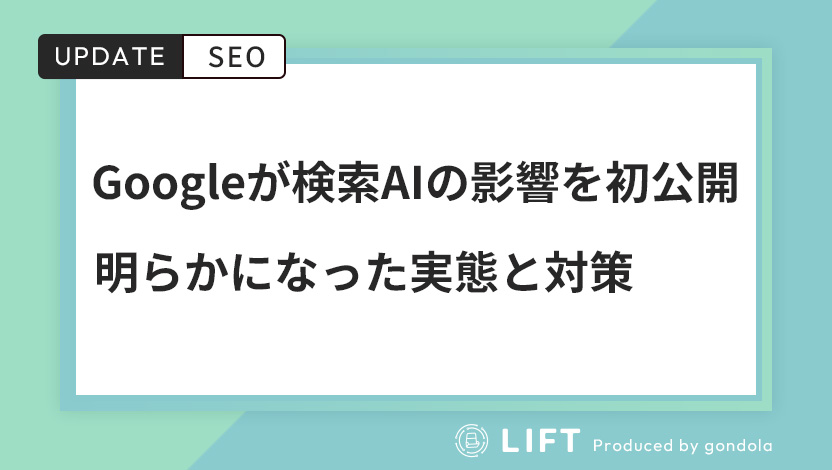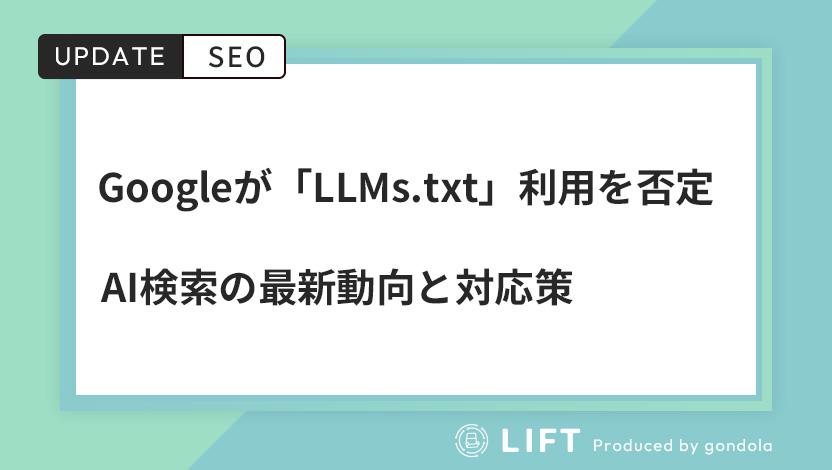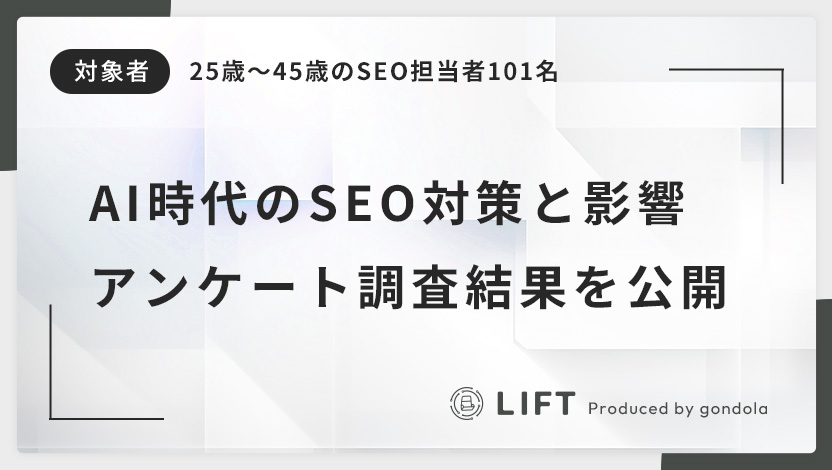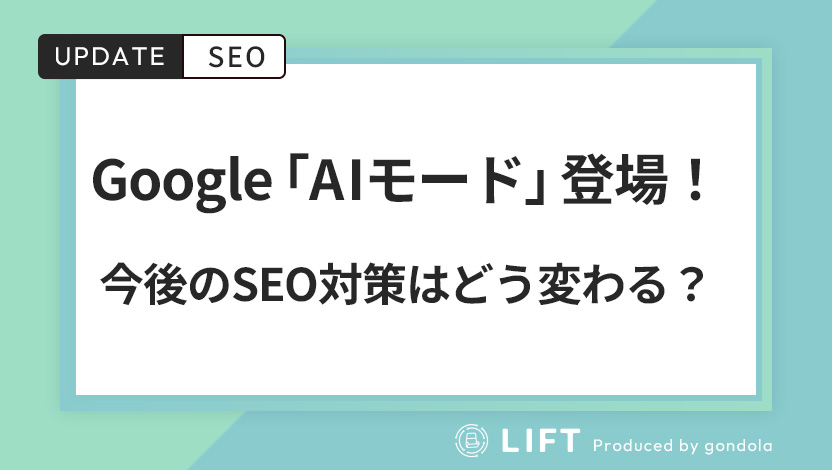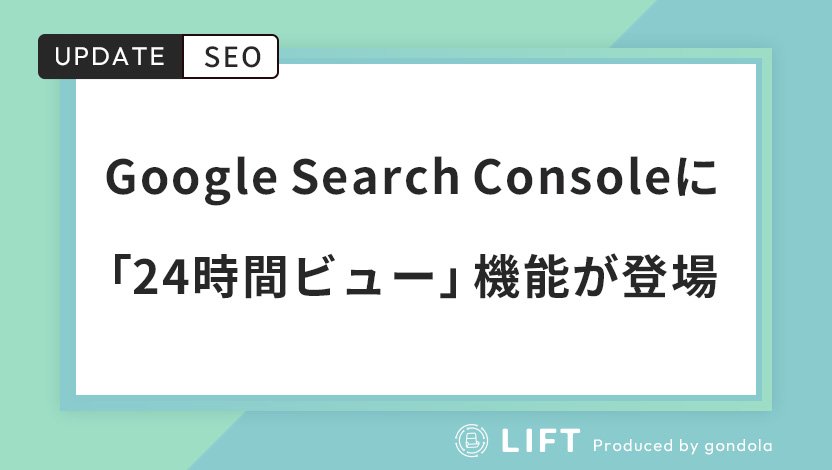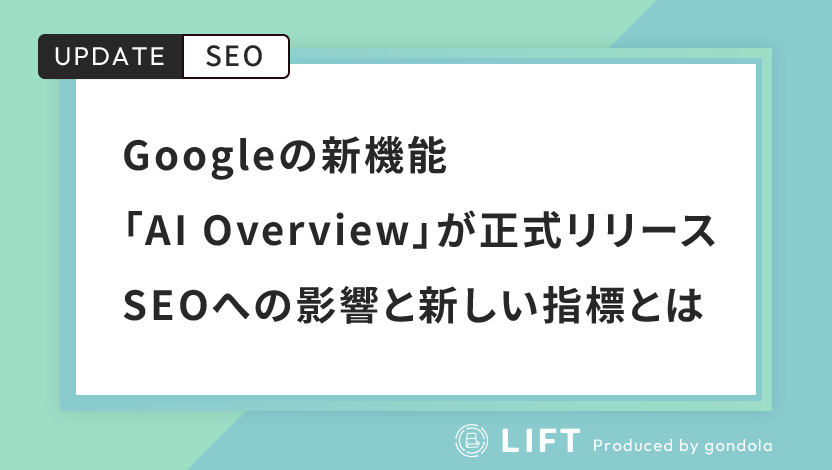ChatGPTやGeminiなどの対話型AIサービスの登場により、インターネットで情報収集をする際のユーザー行動に変化が起きています。従来主流だった「ググる」代わりにAI検索を行う、あるいは検索エンジンとAI検索を併用するユーザーが増えているのです。
この変化を受けて、企業のWebマーケティング施策において「LLMO」の注目度が高まっています。本記事では、LLMOの基本からSEOとの比較、具体的な施策を解説します。
※本記事の内容は、2025年11月13日記事公開時点の情報です。
INDEX目次
LLMOとは
LLMOとは、「Large Language Model Optimization」の略称です。直訳すると、「Large Language Model(LLM)=大規模言語モデル」の「Optimization=最適化」という意味になります。
LLM(大規模言語モデル)は生成AIの一種で、ChatGPTやGemini、Perplexityなどの対話型AIサービスの基盤技術として使われています。LLMOとは、LLMを用いたAI検索において、自社のWebページが引用されやすいよう最適化する施策を指します。
LLMの仕組み
LLMは言語処理に特化したAIモデルです。膨大なテキストデータを学習して、人間が行っているような自然な言語の生成を行います。
LLMはテキストデータを「トークン」と呼ばれる単位に分割して統計的処理しています。トークンは、単語や文字セット、単語と句読点の組み合わせなどです。LLMが一度に処理できるトークン数には上限があります。
LLMに引用されやすいコンテンツの条件
LLMに正確に情報を処理してもらえるよう、Webコンテンツの作成では、以下の点を意識しましょう。
- 冗長な言い回しや重複する表現を避ける
- 箇条書き、Q&A形式を活用する
- コンテンツの意図や結論を最初に明確に示す
- 情報量の多いデータは要約を付ける
こうすることで、生成AIに理解してもらいやすいコンテンツに仕上げられます。
SEOとの違い
SEOは「Search Engine Optimization(検索エンジン最適化)」の略称です。Google検索のような検索エンジンで、自社のWebページが上位表示されるように最適化する施策を意味します。
LLMOはLLMによる引用を目的としており、SEOは検索エンジンによる上位表示を目的としているという点が、両者の大きな違いです。
一方で、LLMOもSEOも最終的に「自社のWebページをクリックして閲覧してもらうための施策」という点は共通しています。
マーケティングにおいてLLMOが必要とされる背景
Webマーケティングにおいて、LLMOの必要性は急速に高まっています。その背景に、ユーザーの検索行動の変化があります。
インターネットでの情報検索の手段にAI検索が加わる
対話型AIサービスが登場して、インターネット検索の手段にAI検索が加わりました。
その結果、Webページへの流入を設計する際は、従来の自然検索・広告・SNSに加えて、AI検索も考慮する必要が生じています。さらに、Googleの「AI Overviews」や「AIモード」は、検索行動や遷移先の選び方にも影響を与えました。
ユーザー行動の変化について参考になる情報として、Googleが2025年8月8日に投稿した記事があります。
この記事では、「AI活用の機能登場後も、Google検索からWebサイトへの自然検索によるクリック総数は、前年比で安定して推移している」と紹介されています。
さらに、「質の高いクリック」の数がやや上昇していることも示されています。「質の高いクリック」とは、Webサイト訪問後にすぐに検索結果へ戻る「早期離脱」をしないクリックのことです。詳細は、上記の参考記事をご確認ください。
SEOとLLMOで共通する内容
実は、SEOの基本的な対策はLLMOにも効果的です。
「Google Search Central」では、以下のように、AI機能に表示されるためには基本のSEO対策を行うことが推奨されています。
SEOのベストプラクティスは、引き続きGoogle検索のAI機能(AIによる概要やAIモードなど)でも有効です。AIによる概要やAIモードにコンテンツが表示されるための追加の要件はなく、別途特別な最適化を行う必要もありません。ただし、SEOの基本のベストプラクティスを再度確認することは常に効果的な方法です。
引用元:AI 機能とウェブサイト | Google 検索セントラル | Documentation
次に紹介するのは、SEOにおいて効果的とされる対策のうち、特にLLMOにも効果的と考えられるものです。
構造化マークアップ
構造化マークアップとは、Webページの作成に使われるマークアップ言語「HTML」の記述方法です。Webページの内容を、Google検索のクローラーが理解しやすくするために行います。
構造化マークアップを行うことで、通常の記述ではクローラーにただの文字列として認識される内容について、「会社名」「質問」といった特定の意味を持たせることができます。LLMOでは「記事」「よくある質問(FAQ)」「組織」に構造化マークアップを適切に使うことで、LLMやAI検索システムに引用される可能性が高まる、という見方が広まりつつあります。
構造化マークアップを実装するには、HTMLに関する専門知識が必要です。参考となる情報として、以下のGoogle公式情報があります。
サイトパフォーマンス最適化
サイトパフォーマンス最適化とは、Webサイトの表示速度を向上させる取り組みです。Webサイトの表示速度は、UX(ユーザーエクスペリエンス)に影響する重要な要素です。Googleの公式情報にはUXに関する以下の記載があります。
Google のコア ランキング システムは、優れたページ エクスペリエンスを提供するコンテンツを高く評価するように設計されています。
引用元:Google Search Central|ページ エクスペリエンスが Google 検索の検索結果に与える影響について
Webサイトの表示速度やUXの高さはGoogleが重視する指標のひとつなので、改善することで評価向上につなげられます。
Webサイトの表示速度を確かめるには、Googleが提供している無料のWebサイト表示速度測定ツール「PageSpeed Insights」が便利です。WebサイトのURLを入力すると、Webサイトの表示速度に加え、改善点についても情報を得ることができます。
比較的すぐにできる改善点は、
- 画像の最適化
- コードの最適化
- データベースの最適化
の3つです。
コンテンツにおける「E-E-A-T(経験・専門性・権威性・信頼性)」
Googleは、Webコンテンツの評価指標として「E-E-A-T」という4つの項目を公表しています。
各項目の意味と、評価を高めるために有効な情報を下表にまとめました。
| 各項目の意味 | 評価を高めるために有効な情報 | |
| E | Experience(経験) | ・実績 ・導入事例 ・ユーザーインタビュー ・レビュー など |
| E | Expertise(専門性) | ・専門的な知見、解説コンテンツ ・認証、資格、受賞歴 など →特に、オリジナルティの高い一次情報が高く評価される |
| A | 権威性(Authoritativeness) | ・サイト外での評価 ・被リンク ・メディア掲載歴 ・サイトトップページ ・会社概要 など |
| T | 信頼性(Trustworthiness) | ・ルールに則った運営者情報や利用規約の記載 ・SSL化 など |
「E-E-A-T」を高めることで、LLMから「このWebサイトの情報は信頼できる」と判断され、ページやコンテンツが引用される可能性が上がります。
また、関連する情報を網羅することも、LLMの理解を助け、そのコンテンツが引用される可能性を上げます。
LLMOならではの対策
前述の基本的なSEO対策に加えて、LLMOならではの対策として、以下の点も押さえておきましょう。
LLMにとって理解しやすいコンテンツ構成
LLMOでは、SEO対策に加えて、以下のようなLLMが理解しやすいコンテンツの構成が重要です。
| 項目 | 説明 |
| 論理的整合性がとれている | 基本は「結論→理由→詳細」という構成。 ノウハウ記事や解説記事などに向いています。 |
| 時系列に沿っている | 「起承転結」の構成。 インタビューや読み物系の記事に向いています。 |
| Q&A形式 | 質問を見出しに、回答を本文で展開する構成。 ユーザーが行いそうな質問を想定して、LLMが回答としてそのまま引用できる文章を意識すると良いです。 |
これらの構成は、LLMだけでなく、人間の読み手にとっても理解しやすいコンテンツです。
LLMs.txtの設置
「LLMs.txt」は、LLMOにおいて一部関係者が提案している実験的な取り組みであり、現時点では成果を裏付けるデータは発表されていません。また、Googleは「LLMs.txt」の利用を公式に否定しています。
そのため、現時点ではLLMOのために「LLMs.txtの設置」を行う必要はありませんが、LLMO関連の話題で頻出する言葉ではあるため、参考までに解説します。
「LLMs.txt」は、自社のWebサイトにどのようなページがあるのかという情報を、LLM向けにテキストファイルで提供する仕組みです。LLMに、Webサイトの構造や内容を正確に把握させることを目的としています。
従来のSEOでは、「robots.txt」を使って検索エンジンのクローラーを制御してきました。「LLMs.txt」は、それと同じ役割を生成AI向けに果たす仕組みとして提案されています。
Googleの「LLMs.txt」に関する発表については、以下の記事を参考にしてください。
LLMOの効果を分析する方法
LLMOの目的は、自社のWebページやWebコンテンツが生成AIに引用される回数を増やし、最終的に自社のWebサイトへの流入を増やすことです。
そのため、LLMOの効果の分析では、主に「生成AIによる引用」と「生成AI経由の流入」について計測します。
生成AIによる引用を調べる方法
実は現時点では、自社のWebページやWebコンテンツが生成AIに引用された回数を正確に測定する方法はありません。
ただし、近いことができるツールとして「Ahrefs」があります。Ahrefsは、AI Overviewsにおけるキーワードや、主要な生成AIツールにおける自社のブランドの表示状況などを確認できるツールです。
また、手動にはなりますが、ターゲットとするユーザーがAI検索でどのような質問をしているかを考えて、実際にAI検索を行ってみるのもひとつの方法です。AI検索をしてみて、自社のWebページやWebコンテンツの引用、自社の社名・サービス名などどの程度登場するかを確認します。
LLMOで効果を出すポイント
LLMO対策の効果を高めるために、以下のポイントを押さえましょう。
最新の情報を確認する
生成AIは進化のスピードが非常に早く、関連する情報も日々アップデートされています。そのため、本記事で解説した情報をベースにしながら、常に最新の情報を確認することをおすすめします。
情報を迅速に追うために、信頼できる情報源をいくつか決めておくと良いでしょう。たとえば、Googleの公式情報はチェックしておいたほうが良い情報源のひとつです。
SEOなど従来の集客施策と両立する
AI検索の利用は増えていますが、ユーザーはそれだけに頼って情報収集をしているわけではありません。むしろ、AI検索という選択肢が増えたことで、インターネット上でのユーザーとの接点はより多様化しています。
ユーザー接点を取りこぼさないために、LLMO対策と並行して、SEO対策や広告出稿、SNS運用など、従来の集客施策もきちんと継続していく必要があります。LLMO対策とSEO対策には共通するところが多いので、従来通りで問題ないところはそのまま継続して、効率的に対策を行っていきましょう。
また、LLMO対策を行いながら、他の集客施策の効果を分析することで、どの施策にどれだけ注力すれば良いかの参考になります。
従来のSEOの基本とコンテンツ制作時のLLMO対応を意識
LLMO対策は特別な新しいことではなく、従来のSEO対策の延長線上にあります。本記事で解説したように、SEO対策の基本を押さえながら、コンテンツ制作時はLLMOに対応する文章や論理展開を意識しましょう。
Google公式は、LLMOのための特別な対策は必要ないと明言しています。AI検索が増えているからといって、これまで積み上げてきたWebマーケティングの経験やノウハウが無駄になるわけではありません。
これを機会にSEO対策の基本をきちんと押さえられているか、改めて確認してみましょう。
また、LLMOを意識することは、人間にとって理解しやすいコンテンツを作ることにもなります。LLMOを行うことは、そもそも読者にとってわかりやすいコンテンツを提供できているかを見直すチャンスでもあります。
弊社ゴンドラでは、LLMO対策として様々な手法に取り組み検証しております。
- クローラーのLLMS.txtへのアクセスの集計をして、LLMS.txtの有効性の確認
- 流入経路分析と流入コンテンツからのLLMに効果的なコンテンツの企画や制作
上記のように、LLMOでお困りの方はお気軽にお問い合わせください。
CONTACT お問い合わせ
WRITING 執筆
LIFT編集部
LIFT編集部は、お客様との深いつながりを築くための実践的なカスタマーエンゲージメントのヒントをお届けしています。