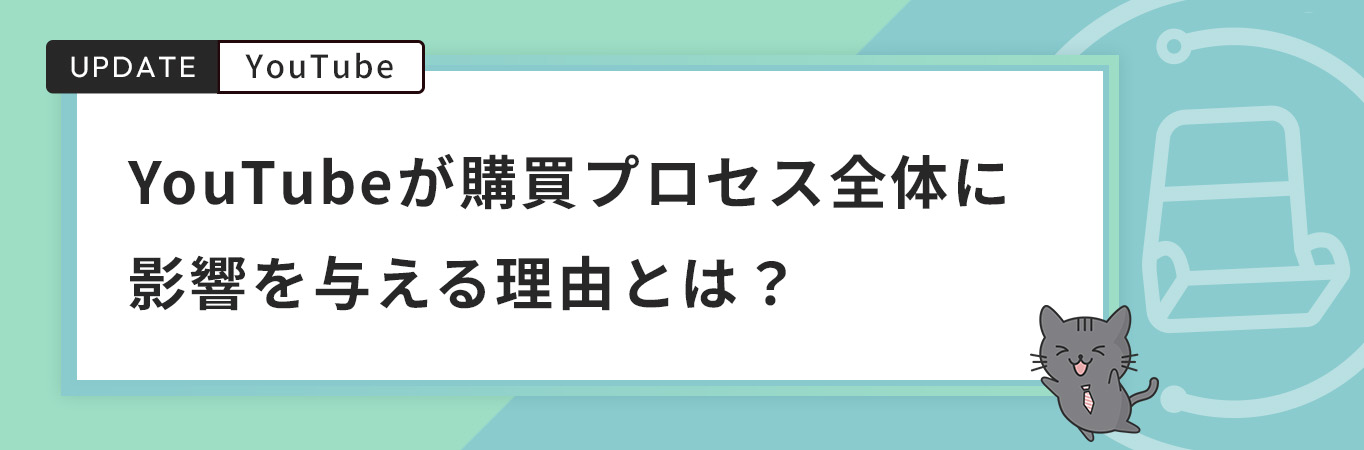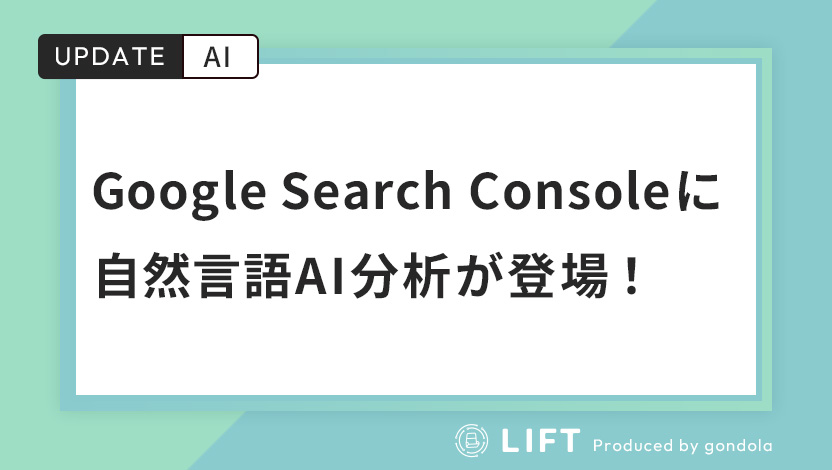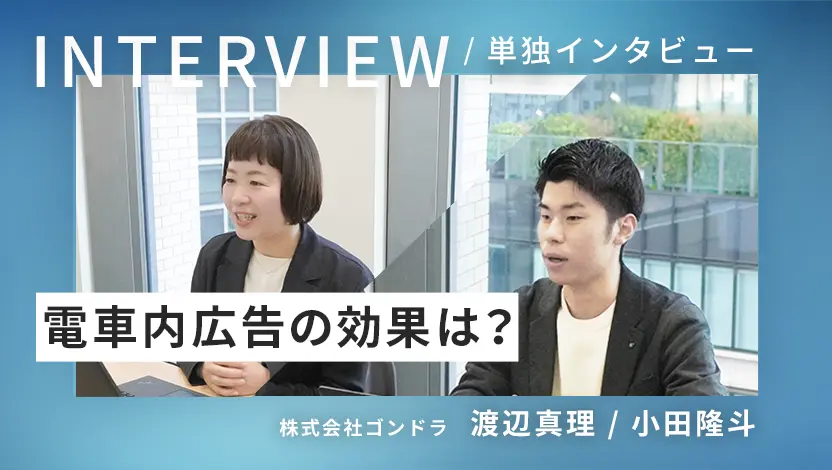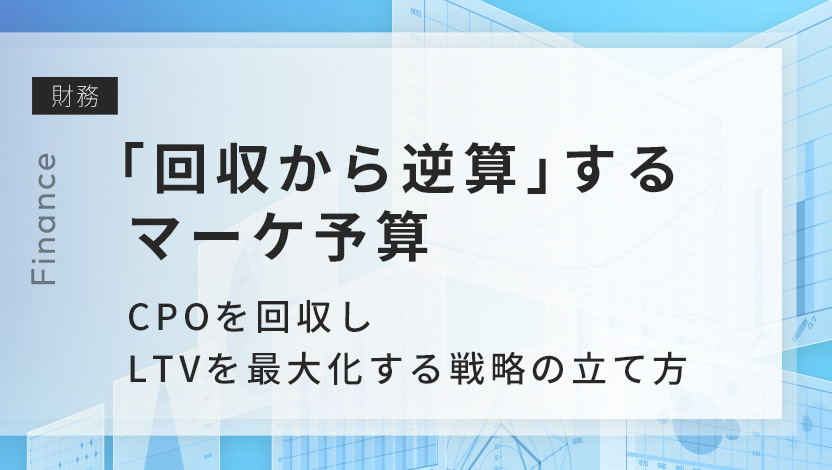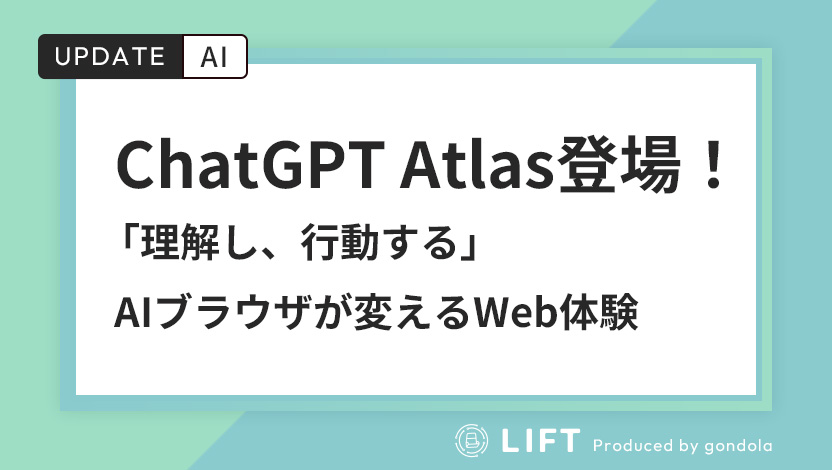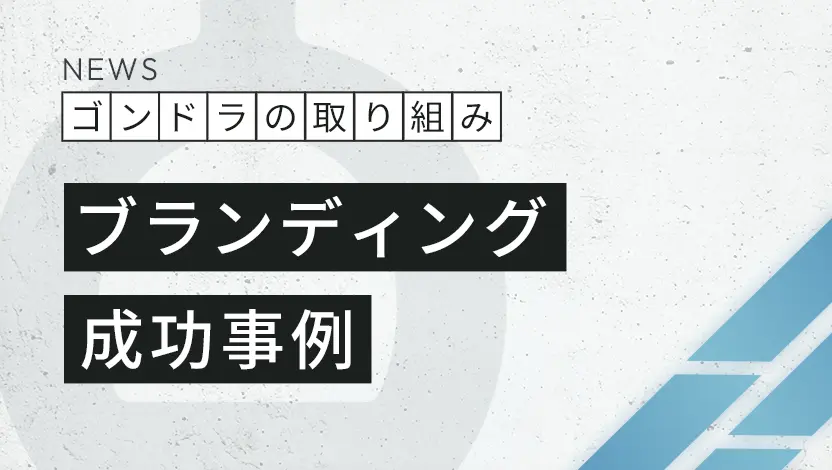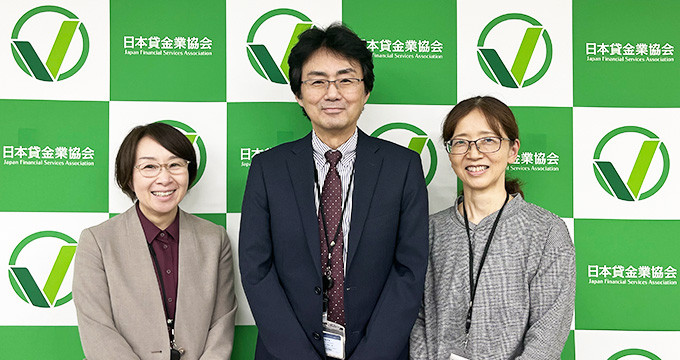YouTubeが購買行動に与える影響力が、マーケターの想定をはるかに超えていることが明らかになりました。単なる「認知獲得の場」ではなく、興味の喚起から比較検討、そして最終的な購入決定まで、購買プロセス全体に深く関与するようになったのです。
本記事では、Googleの記事(※1)をもとに、YouTubeがどのように購買行動に影響を与えているのか、そして今後マーケターがどのように戦略を転換すべきなのかを解説します。
INDEX目次
YouTubeは「購買に影響を与えるプラットフォーム」へ
もともと、YouTubeは趣味の延長で動画を投稿する場として始まったプラットフォームでした。現在は、200億本以上の動画を視聴できる巨大なメディアへと成長し、スマートフォンよりも、テレビにインターネットを接続してYouTubeを見る「コネクテッドTV」での視聴が多くなっています。
リビングルームの大画面でじっくりと動画を視聴する行動は、動画の役割そのものを変えました。こうした環境の変化によって、動画はもはや「商品を知ってもらうためのもの」ではなく、「購買行動全体に影響を与える存在」へと変わったのです。
データで見る、動画が購買に与える影響力
Googleの記事で紹介されているボストン・コンサルティング・グループ(BCG)の調査(※2)から、動画が購買プロセスのどの段階にどれほど影響を与えているのか、具体的な数値をみていきましょう。
動画は購買ファネルの「下流」にも深く関わっている
実際にアメリカの1万人の購買行動を分析した結果、動画が購買プロセス全体に与える影響の大きさが数値として明らかになりました。
動画が「商品の購入に興味を持たせた」と答えた人は43%、「ブランドを知るきっかけになった」が50%、「購入するブランドの選択に役立った」が45%、「購入を後押しした」が34%にのぼりました。
この数字から、動画が購買ファネルの”上流”だけでなく”下流”、つまり購入決定の瞬間にも深く関わっていることがわかります。動画は認知から購入まで、あらゆる段階で消費者の意思決定に影響を与えているのです。
YouTube広告は影響力が非常に高い
さらに注目したいポイントは、プラットフォーム間に影響力の差がある点です。
他のSNSに比べ、YouTubeはブランドの比較検討において1.7倍、購買決定において1.6倍も良い影響を与えていることがわかりました。
現時点では、YouTubeを単なる広告枠としてしか見ておらず、影響力を活用しきれていないマーケターは多いかもしれません。従来のファネルを前提にしたメディアプランのままでは、YouTubeが購買プロセス全体で果たす非常に大きな役割を見落としてしまう可能性が高いでしょう。
購買プロセスはより複雑で循環的なものへ
こうした購入体験の変化の背景には、AIの急速な普及と進化が深く関わっています。生成AIの普及により、消費者が情報を探索し、比較検討する方法が根本的に変わりつつあるのです。
ボストン・コンサルティング・グループ(BCG)は、現代の購買行動を「ファネル」と呼ばれる従来の直線的なモデルでは説明できない(※3)と指摘しています。
これまでの購買プロセスは、認知から興味、比較検討を経て購入へと段階的に進む一本道として捉えられていました。しかし実際の消費者行動はもっと複雑です。
「サーチング」「ストリーミング」「スクローリング」という3つの行動
Googleは、買い物につながる人々の情報行動を「サーチング」「ストリーミング」「スクローリング」という3つに分類(※4)しました。
- サーチング
→画像検索や動画検索、対話型検索を利用して意図に合った情報を導き出す行動 - ストリーミング
→レビュー動画などを通じて商品購入の疑似体験をする行動 - スクローリング
→自分向けに流れてくる情報の中から新しい発見を得る行動
人々はこれらの行動を行き来しながら、より複雑で循環的なプロセスをたどっているというのです。
受動的かつ能動的な情報行動「情報ドリフティング」
気をつけておきたいのが、これら3つの行動に決まった順序がない点です。
すべての行動が新しい選択肢と出会うきっかけであり、購入に直結する可能性もあります。つまり、個々人に対して適切な情報さえ提供できれば、認知から購入まで瞬時に発生する可能性もあるのです。
さらに、これらの行動は特定のプラットフォームに限定されません。サーチングは検索サイトだけでなくSNSやECサイトでも発生し、ストリーミングは動画配信サービス以外でも、スクローリングはSNS以外でも行われています。
Googleはこうした複雑な情報行動を「情報ドリフティング」と名付けました。これは、押し寄せる情報の流れに身を任せつつも、自分にぴったり合う情報を求めてコントロールする、受動的かつ能動的な消費者の姿を表しています。
消費者自身が「自分にとっての答え」を得る時代へ
情報ドリフティングによって、消費者は自分に合った選択肢を自ら見つけ出せるようになりました。AIが情報を整理してくれるため、膨大な情報の中から「自分にとっての答え」を導き出すことが、マーケターだけでなく消費者自身にもできるようになったのです。
結果として、買い物での後悔が減り、満足度が高まるだけでなく、新たな発見や体験へとつながる可能性も広がっています。
複雑な購買プロセスでYouTubeが選ばれる理由
複雑化した購買プロセスの中で、なぜYouTubeが他のプラットフォームよりも高い影響力を持つのでしょうか?
その理由を3つの価値基準から解説します。
YouTubeが購買に影響する理由は「注目」「関連性」「信頼」
BCGは、YouTubeがこれほど購買行動に影響する要因を「注目」「関連性」「信頼」の3つであると説明しています。
- 注目:数多くの情報の中でどれだけユーザーの視線を引きつけるか
- 関連性:その動画の内容が自分の興味や状況にどれだけ合っているか
- 信頼:情報が信頼できるか、またその情報を発信する人に親しみや安心感を持てるか
この3つのバランスが整ったとき、ユーザーは「自分で選んだ」と納得して購買行動を起こします。従来の広告のように一方的に押し付けられるメッセージではなく、自分で見つけて選んだという感覚が、購買意欲を高める重要な要素なのです。
YouTubeはすべての要素が他プラットフォームを上回る
BCGの分析によると、YouTubeは「注目」「関連性」「信頼」の3つすべてが他のプラットフォームを上回っていました。他のSNSに比べると、注目を1.5倍、関連性を1.7倍、信頼性を2倍高く感じさせているという結果が出ています。
なぜ、YouTubeはこれほど高い評価を得ているのでしょうか?
その要因は、
- 長尺コンテンツを通じてストーリーや価値観を深く伝えられること
- クリエイターへの信頼感が強いこと
の2つです。
Googleの記事(※5)では、YouTubeのクリエイターのおすすめは他のプラットフォーム上のインフルエンサーのおすすめよりも98%信頼されているという結果も示されています。つまり人々はYouTubeを「大量の情報の中の1つ」ではなく、「信頼できるガイドのような存在」として捉えているのです。
マーケティング戦略 は「リーチ」から「つながり」へ
YouTubeの影響力を最大限に活用するために、マーケターはどのような戦略転換が必要なのでしょうか?
最後に、これからの時代に求められるマーケティングの考え方を整理します。
成功のカギは「注目・関連性・信頼」への転換
ここまでの流れをふまえると、企業がマーケティングを成功させるには、単にリーチを追い求めるのではなく、「注目」「関連性」「信頼」を築き上げる必要があることがわかります。
今の消費者の心は、ただ広告を見るだけでは動かされません。自分の興味にマッチし、共感でき、信頼できるクリエイターやブランドとの”つながり”を求めているのです。
YouTubeは、長尺動画・ショート動画・ライブ配信など、さまざまな形式でターゲットとのつながりを築ける、今もっとも強力なプラットフォームです。コンテンツやフォーマットの垣根を越えた表現の場を提供することで、ブランドが人々と深くつながる機会を生み出すことが大切です。
これからの時代に求められるマーケティングとは?
これからの時代に求められるのは、「インプレッション(表示回数)を買うこと」ではなく、「印象(心に残る体験)をつくること」です。
「動画広告を配信すること」自体を目的にしてしまうと、目指している成果は得られません。「視聴者の記憶に残り、購買行動を変えるようなコンテンツを設計できるか」が成果を大きく左右します。
これからは、人の心の動きに寄り添うストーリーテリングが、いっそうマーケティングにおいて重要になっていきます。最新のAI技術を追いつつ、ユーザーにとって本当に価値のある体験を提供するための動画マーケティング戦略を構築していきましょう。
CONTACT お問い合わせ
WRITING 執筆
LIFT編集部
LIFT編集部は、お客様との深いつながりを築くための実践的なカスタマーエンゲージメントのヒントをお届けしています。